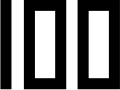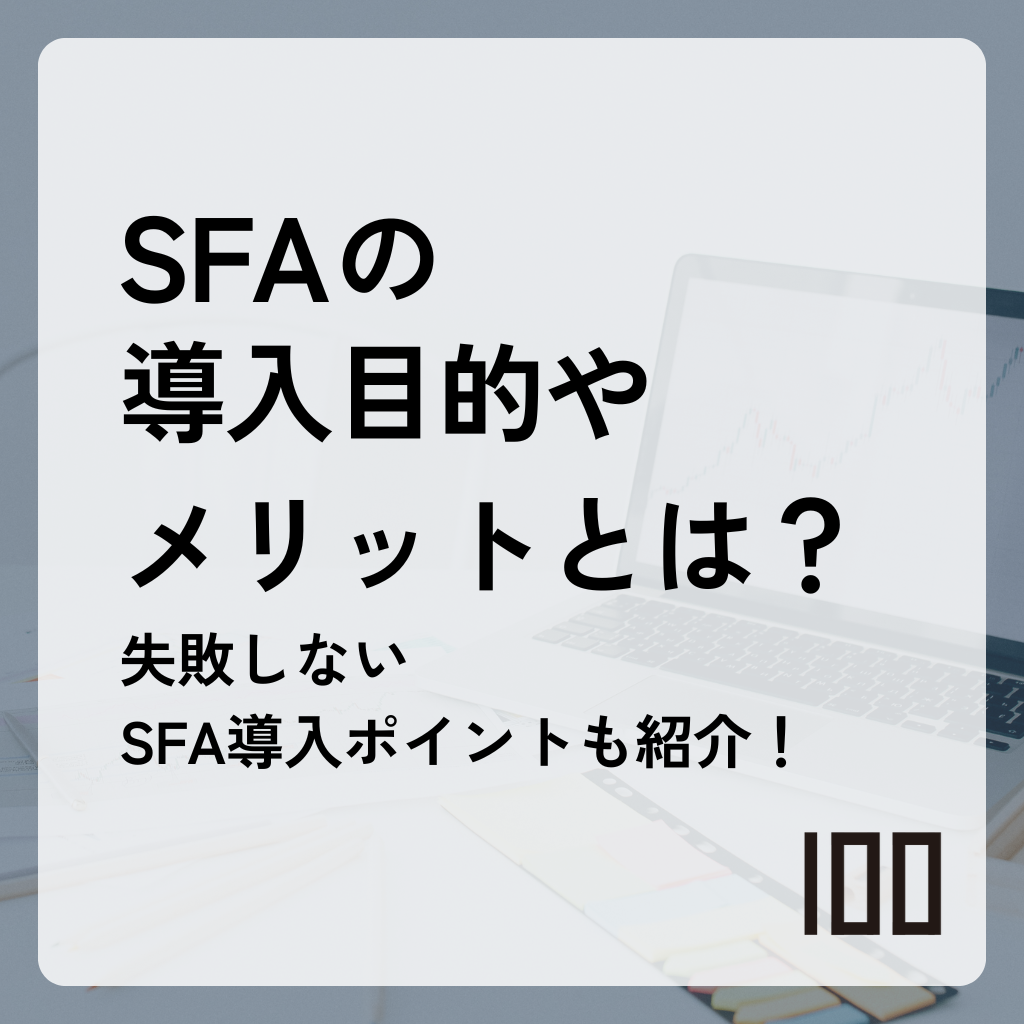

ITを活用して営業活動の効率化を図る「セールステック」市場は、DX推進の流れが追い風となり、近年ますます規模が拡大しています。なかでも、営業部門の課題解決において重要な役割を担う「SFA(営業支援システム)」は、導入企業が増加しているツールの1つです。
キーマンズネットが日本国内のビジネスパーソンを対象に行った調査では、営業部門が抱える課題が明らかになっています。アンケートで上位5つに挙げられた問題点は、「情報の共有と有効活用」「営業活動の効率化」「営業力の強化」「商談、案件管理」「営業担当者のスキル向上」でした。
これらの課題は、営業活動にまつわる情報を管理・共有し、業務の効率化を実現するSFA(営業支援システム)で解決できる可能性があります。
そこで本記事では、SFAの導入を成功させられるよう、導入目的やメリット、失敗しないポイントなどを解説します。「SFAの導入を検討しているが、うまくいくか不安」「SFAで自社の課題は解決できるのだろうか」とお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
そもそもSFA(営業支援システム)とは
SFA(営業支援システム)は、商談情報や活動状況を管理・共有し、営業活動の効率化を図るためのITツールです。以下では、SFAの概要やCRMとの違い、国内における導入率を紹介します。
SFA(営業支援システム)とは
SFAは「Sales Force Automation」の略語で、日本語では「営業支援システム」と呼ばれています。主な機能として、営業担当者の活動管理や案件・商談の進捗状況管理などが搭載されており、営業活動の全体像を把握するのに役立ちます。
商談結果や売り上げデータなどの蓄積・分析もできるため、得られた結果を人材育成や意思決定に生かすことも可能です。営業部門の生産性向上はビジネスの成長に欠かせないことから、近年では日本国内でもSFAを導入する企業が増加しています。
SFA(営業支援システム)とCRM(顧客管理システム)の違いは?
営業組織において、SFAとともによく活用されるツールの1つがCRMです。実際、SFA機能を内包したCRMを「CRM/SFAツール」として提供しているベンダーも多く存在します。
両者は活用場面や機能に重複する部分が多いものの、活用目的に大きな違いがあります。
CRMの目的は、顧客満足度の向上を図り、既存顧客を維持することです。顧客の基本情報はもちろん、企業との接触履歴も含めて一元管理することにより、マーケティングチームや営業チームは顧客体験の向上につながるアプローチを実現できます。
一方、SFAの目的は、営業プロセスを可視化し営業活動全体の効率化を図ることです。SFAはパイプライン管理ツールと売り上げ管理ツールによって構成されており、マネージャーは売り上げや見込み客に関するデータ、営業担当者のパフォーマンスなどを明確に把握できます。
SFAの導入率
日本国内のSFA導入率は、TSUIDEが行った「SFA・CRM導入実態に関する調査」で把握できます。全国の30歳から69歳の男女計14,035人を対象に行ったアンケート結果によると、SFA・CRMツールを「導入している」と回答したのは9.1%、「導入していない」と回答したのは90.9%であることがわかりました。

出典:SalesZine「SFA・CRM導入実態に関する調査/TSUIDE」を基に作成
SFA・CRMを「導入している」対象者へツールの活用度合いを尋ねたところ、73%が「ツールを効率的に活用できている」と回答しました。

出典:SalesZine「SFA・CRM導入実態に関する調査/TSUIDE」を基に作成
ツールを活用できていない対象者がその理由を回答した結果では、「使い方・操作が難しい」(22.7%)、「機能を使いこなせない」(20.6%)が全体の約半数を占めています。

出典:SalesZine「SFA・CRM導入実態に関する調査/TSUIDE」を基に作成
本調査結果から、日本国内におけるSFAの導入率は決して高くないことがわかりました。しかし、導入している企業の7割以上は効率的に活用できていることから、今後はSFA導入企業と未導入企業のデータ活用格差が広がっていくと考えられます。
また、ツールの活用率は、使い方・操作の難易度や過剰な機能によって低下していることがわかります。ツール選定の際は、現場の使いやすさを重視し、組織にとって本当に必要な機能を見極めることが大切だといえるでしょう。
なぜ企業はSFA(営業支援システム)を導入するのか?
デジタル技術が進歩し、DXの重要性がさかんに叫ばれるようになった近年では、ITを活用した営業活動効率化の流れが加速しています。日本国内における浸透率は十分でないものの、世界をリードするグローバル企業では、SFAの活用が当たり前のものとして定着しつつあるのが現実です。
以下では、企業がSFAを導入する理由を大きく4点に分けて解説します。
営業生産性向上のため
SFAを導入する最大の目的は、営業組織の生産性向上を図ることです。SFAによって営業生産性が向上する理由は、大きく以下の2つに分けられます。
営業担当者の活動状況が可視化される
SFAを導入することで、営業担当者の活動状況が可視化されます。どのような業務に、どの程度の時間が使われているのかを把握できるため、非効率性が生じている部分へ改善のアプローチが可能になるのです。
日本企業では組織全体での協調を重視する営業スタイル・組織文化が一般的なので、個人ごとに明確な責任や役割が定義されていないことがあります。グローバル企業においては1人の営業担当者が実施している業務を、日本企業では複数人で分担しているケースも少なくありません。結果として1つの業務にかかわる人数が増え、調整に時間を取られることで営業効率性の悪化を招いています。
SFAによって各担当者の動きが見える化されると、業務における「無駄」が浮き彫りになります。その結果、個人の活動が最適化され、ひいては組織全体の生産性向上につながるのです。
営業活動以外の社内業務に費やす時間を削減できる
SFAには報告業務や資料作成、数値面の管理・分析などを効率化する機能が搭載されているため、顧客対応以外の社内業務に割く時間を削減できます。
マッキンゼーが複数の日本企業において営業の業務時間を調査した結果によると、会議への出席、営業日報・週報・月次報告、稟議書作成、その他社内資料の作成といった業務の占める時間は全体の2~4割に及ぶことがわかりました。

出典:McKinsey&Company「日本の生産性はなぜ低いのか」を基に作成
この数値はグローバル企業のベストプラクティスと比較すると1~2割程度多いことから、日本企業の生産性に課題があることが読み取れます。
営業活動以外の社内業務を紙やExcelベースで行っていては、作業の非効率性を改善できません。SFAの機能を有効活用することで、顧客への営業活動(売り上げに直結する活動)に集中できる時間を増やし、営業生産性の向上を図ることが重要です。
データを会社の資産とするため
SFAを導入すると、顧客との接触履歴や過去の提案内容、失注理由などの情報がデータとして蓄積され、戦略立案の参考材料として活用できるようになります。
これらのデータは顧客と接するなかで得られた「生」の情報であり、他社には知り得ない自社独自の資産です。SFAに蓄積することなく各営業担当者が属人的に情報管理を行うと、組織単位でのデータ活用が困難になり、企業にとっての損失につながります。
SFAによる情報管理は、ノウハウの蓄積につながるという側面もあります。たとえば受注に結び付いた商談と失注した商談の履歴(商談に至った経緯、提案内容、顧客の納得感など)を蓄積することで、成功に向けた「勝ちパターン」を見出すことが可能です。
蓄積したノウハウは、ナレッジとして人材育成に活用できます。各営業担当者のスキル標準化にもつながるため、結果として組織全体の営業力向上に寄与するでしょう。
顧客満足度向上
SFAを導入することで営業プロセスが透明化するため、顧客満足度を向上させるうえでの基盤が整います。
案件の進捗状況や対応履歴が可視化され、組織内で共有されると、担当者間の引き継ぎが容易になります。その結果、アプローチの重複を防止できたり、最適なタイミングでの提案が可能になったりと、一気通貫した高品質な顧客対応が実現するでしょう。
さらに、SFAによって情報共有が活性化すると、各営業担当者とマネージャーは相互理解を図りながら業務を進捗できるようになります。営業部隊がより充実した営業活動を実施することで、顧客満足度はおのずと向上するものです。
売り上げ増加
前述したとおり、SFAの導入によって企業は以下のようなメリットを享受できます。
- 営業活動以外の業務に費やす時間を削減でき、コア業務にリソースを集中できる
- 営業担当者の活動状況を可視化することで、個人の時間の使い方を最適化できる
- データ活用や情報共有が活性化することで、営業活動全体の品質が向上する
このように、SFAには営業の「活動時間」および「品質」を向上させる効果があるため、活用を促進することで成約率の改善が見込めます。つまり、SFAによる営業改革が、企業全体の売り上げを大きく左右するといっても過言ではありません。
SFA(営業支援システム)の基本的な機能
SFAに搭載されている代表的な機能は以下のとおりです。
- 顧客情報管理
- 案件管理
- 商談管理
- 営業活動管理
- 売り上げ予測
SFAの導入時に機能を最大限に活用できるよう、それぞれの詳細を確認しておきましょう。
顧客情報管理
SFAの主要な機能の1つが「顧客情報管理」です。顧客の会社名や電話番号、役職といった基本情報をはじめ、商品の購買履歴や企業との接触履歴などを一元管理できます。

出典:HubSpot
顧客から問い合わせがあった際、SFAに蓄積している顧客情報を参照すれば状況を一目で把握でき、担当者以外でもスムーズなコミュニケーションを実現可能です。
顧客に関する詳細情報は属人化しやすく、担当者の異動や退職などの際に顧客へストレスを与えてしまうことが少なくありません。SFAで顧客管理を行うことで、引き継ぎ時のトラブルを最小限に抑えられることに加え、組織全体で顧客をフォローする体制が整えられます。
案件管理
SFAには、見込み客へのアプローチから受注につなげるまでの一連の情報を管理する機能が搭載されています。個々の案件に対して、営業先情報、営業担当者、提案内容(商品・サービス)、見積もり額、営業フェーズ(進捗)、受注見込み(成約確度)、受注予定日などの関連情報を管理可能です。

出典:eセールスマネージャー
マネージャーは、SFAの案件管理画面をチェックすることで、各案件の状況を俯瞰できます。「どの営業担当者が」「どの営業先に」「どのような商品をいくらで提案し」「現在どのような状況にあるのか」を一目で把握できるため、適切なタイミングで適切な内容の指示出しが可能になるのです。
また、SFAに各担当者が入力した情報が自動的に上司やマネージャーに共有されることで、電話やメール、書面による報告業務の時間削減につながります。状況報告がスムーズに進むことは、質の高い営業会議を実現するうえでも効果的です。
商談管理
商談管理とは、案件化した商談の進捗を詳細に管理することです。具体的な管理項目としては、過去の履歴、商談の目的、商談内容(顧客が抱えている課題や提案した解決策など)、商談時間、決裁者、提案書、商談進捗、次回アクション予定などが挙げられます。

出典:売上UP研究所
案件管理と重複する部分もあるものの、商談管理では主にコミュニケーション情報に焦点が当てられます。成約に至った商談と失注した商談の情報を比較・検証し、成功モデルをナレッジとして蓄積することも可能です。
商談の進め方や提案書の作成方法、クロージングの流れなどをチーム内で共有すれば、部門全体のレベルアップにつながるでしょう。
営業活動管理
SFAでは、営業担当者の活動を記録・管理することもできます。コール数、アポイント件数、訪問件数、受注率、行動予定など、日々の行動および結果を数値化して管理可能です。

出典:ネクストSFA
マネージャーは営業活動管理情報を見れば、各営業担当者の業務効率性を定量的に比較できます。「成績が伸び悩んでいるメンバーの行動から無駄や問題点を見つけ出す」「成績の良いメンバーのデータから効果的な行動を導き出し、他のメンバーに共有する」といった活用方法が有効です。
担当者間の業務量調整にも役立つため、リソースを生産性の高い業務に集中でき、部門の営業効率向上につながります。
売り上げ予測
SFAには顧客や案件、活動の情報の管理機能だけではなく、蓄積した情報の集計・分析機能も搭載されています。なかでも営業組織で特によく活用されるのが、売り上げ予測機能です。

出典:ネクストSFA
案件ごとの確度や受注見込額から、リアルタイムに精度の高い数値を導き出すことができます。メンバーごと、部署ごとの売り上げだけではなく、商品・サービス別や顧客別、期間別などさまざまな角度から数値を算出可能です。
正確な売り上げ予測があることで、マネージャーは優先度の高い案件を把握し、部門内のキャスティングを最適化できます。「確度は高くないものの受注見込額が高い」という案件には実力のあるメンバーを配置するなど、戦略的なマネジメントを実現可能です。
SFA(営業支援システム)導入に失敗しないためのポイント
SFAの導入は、組織に完全に定着することで初めて「成功」といえます。以下では「せっかくSFAを導入したのに使いこなせず、システムが形骸化してしまった」という失敗を防ぐうえで、おさえておくべきポイントを7点紹介します。
スモールスタートする
SFAを導入する際は、初めから大規模に運用を開始するのではなく、一部の部署から導入して様子を見ることが大切です。全部署への一挙導入は、コストや組織への適応などの面でリスクが大きくなります。
選定段階で条件がマッチする製品であっても、実際に導入するまで組織との相性は図れません。まずは一部の部署(担当者)をピックアップしてテスト運用を行い、操作性や機能性を確認しましょう。
導入をスムーズに進めるポイントは、テスト運用で問題点を明確にし、入力項目や運用ルールなどを整備したうえで全部門へ展開することです。トライアルやデモなどを積極的に活用しつつ、段階的な導入を心がけることをおすすめします。
SFAの設計は可能な限りシンプルに
SFAでは、入力する情報の項目を増やすほどデータ量が増加し、より精度の高い分析結果を導き出すことができます。ただし、現場の作業負担も入力項目の多さに比例して増えることを考慮しておかなければなりません。
SFAは、現場の営業担当者が情報を入力することで初めて機能します。SFAの操作や情報入力が現場の時間的・精神的負担になってしまうと、ツールの形骸化を招きやすくなるため注意が必要です。
実際、SFAの現場活用に「課題あり」と回答した企業のうちの52.2%が「入力する作業負担が大きい」ことを理由として挙げている調査結果もあります。SFAの導入時には「本当に集計すべきデータは何なのか」を社内で十分に検討し、可能な限りシンプルな設計を心がけることが大切です。
SFAの運用担当者を設ける
SFAの導入期には疑問やトラブルの発生が多くなるため、SFAの専任担当者を設置することをおすすめします。
ベンダーが提供する導入サポートもあるものの、基本的には自力でマニュアルを読み込んだり、動画を閲覧したりして課題解決するものがほとんどです。問い合わせ対応もオンラインによる遠隔サポートが多く、課題発生時にリアルタイムな対応が実現するとは限りません。
問題が発生した際に迅速に解決できる体制が整っていないと、現場はSFAの運用を負担に感じてしまい活用が促進されません。使い方や操作に関する質問、設定変更の要望などに備え、すぐに社内で相談できる体制を整えておくことが、SFAの定着において非常に重要です。
運用ルールを設ける
SFAを有効活用するためには、社内における運用ルールの言語化が重要です。ルールが設定されていないと、営業担当者はそれぞれ異なった基準で情報を入力するため、登録されたデータの利用価値がなくなってしまいます。
データが最新化されない、そもそもデータが入力されないといった問題が発生すれば、SFAの導入は失敗に終わります。このような事態を防ぐうえでは、以下のようなルールを策定することが有効です。

実際の運用においては、すべてに一律の基準を設けることが必ずしも正解とは限りません。現場の状況をふまえたうえで、自社に最適なルールを検討しましょう。
目的から逆算してツールを選定する
SFAを選定する際は、事前に導入の目的を明確にしましょう。SFAで「どのような課題を解決したいのか」「何を実現したいのか」を明らかにすることで、組織に必要な機能やプランを選択できるようになるためです。
導入目的が不明瞭なままでは、オーバースペックな製品や機能が物足りない製品を選んでしまう可能性があります。実際に、SFAが組織に定着しない原因として「機能の過不足」が挙がるケースは少なくありません。
単に費用のみを比較するのではなく、自社で解決すべき課題や目的から逆算して必要な機能を洗い出し、ツールを選定することをおすすめします。
定期的な社内トレーニング
SFAは導入時だけではなく、定期的に社内トレーニングを実施することで定着しやすくなります。特にSaaSのSFAはアップデートが多く、機能やUIに変化が生じることがあるため、常に最新情報を社内で共有できる体制を構築することが重要です。
トレーニングを実施する際は、SFAの活用によって得られた成果を積極的に現場へ共有しましょう。定期的にSFAの必要性を訴求することで、営業担当者の認識がより強化され、活用し続けるモチベーションが保たれます。
PDCAを回しながら運用を改善
SFAを導入した後は、定期的に効果測定を行います。導入当初に期待した成果を得られているのか否かを検証し、運用を改善し続けることが営業活動の効率化には不可欠だからです。
効果を検証する際は、KPIやKGIといった数値目標をあわせて確認することで、改善すべき部分がより明確になります。現場から上がる意見や要望も漏らさず拾いつつ、運用ルールを定期的にブラッシュアップしてSFAの効果を最大化させましょう。
SFA(営業支援システム)の導入ステップ
SFAの導入は、正しい手順を踏んで行うことが大切です。以下では、大きく7つのステップに分けてそれぞれのポイントを解説します。
社内でプロジェクトチームを立ち上げる
まずは、SFAの導入プロジェクトチームを社内で立ち上げることから始めます。営業活動を網羅している人材からプロジェクトリーダー、ITに精通している人材からプロジェクトメンバーをそれぞれ選抜しましょう。チームの人数は、企業規模にあわせて2~5名程度で編成するのが望ましいです。
SFAの導入に際し、新たな業務や既存の業務フローへの変更が生じることで、社内から反発が起こる可能性があります。経営トップ層や役員などから総責任者を選出し、プロジェクトチームをバックアップすることも、混乱を最小限に抑える手段として有効です。
導入目的の言語化
自社にとって必要な機能要件を明確化するために、SFAの導入目的を言語化します。営業改革で達成すべき事項を経営トップと共有しながら、「どのような課題を達成するためにSFAを用いるのか」を明らかにしましょう。
その際、プロジェクトメンバー以外の営業担当者にも日々の課題感をヒアリングしておくと、より多角的な視点で問題点を抽出できます。
導入目的の設定例は以下のとおりです。
- 残業時間を削減するために、報告業務や文書作成をデジタル化して効率化を図る
- 受注率を向上させるために、部門間の情報共有を促進して応対品質を改善する
- 営業戦略の立案を迅速に行うために、データの集計・分析スピードを向上させる
SFA(営業支援システム)の選定
言語化した導入目的を達成するために必要な機能や期間、予算などを検討し、最適なシステムを選定します。具体的な検討項目は以下のとおりです。
- 契約から運用開始、定着までに必要な期間が自社のニーズと合致しているか
- 運用形態はオンプレミス型か、クラウド型か
- 年間予算やシステム活用人数から逆算して、初期費用やランニングコストは適正か
- 導入目的を達成するうえで必要な機能がすべて搭載されているか
- 研修やコンサルティングなど、システム定着のために必要なサポート体制は十分か
- 運用開始後に業務フロー等の変更が発生した場合、それに柔軟に対応できる拡張性はあるか
- 営業現場の業務負荷を考慮したうえで無理なく運用できるか
複数のシステムを比較する際、より詳細な検討材料を収集したい場合は、RFP(提案依頼書)をベンダーに提出することも有効です。
SFA(営業支援システム)の初期設定、構築
導入するシステムが決定したら、運用に向けて初期設定・構築を行います。SFAは、自社の営業実態に沿ってカスタマイズできる製品がほとんどです。営業プロセスを可視化し、各プロセスに必要な業務を定義したうえで、顧客データの登録や各種マスタ、パラメータ情報などを設定しましょう。
その際は、SFAをスムーズに組織へ定着させるためにも、現場の使いやすさを重視した設計を心がけることが大切です。運用ルールにおいては社内への周知徹底が必要なため、しっかりとドキュメント化して共有できる体制を整えておきます。
SFA(営業支援システム)の社内体制を構築
SFAの運用を軌道に乗せるうえでは、社内体制を構築することも重要です。大きく以下4つのポイントをおさえて取り組みましょう。

導入する前に社内でのトレーニングを実施
社内への本格導入に先立って、SFAを活用する全ユーザーを対象にトレーニングを実施します。操作方法の説明はもちろん、SFA活用の意義や期待できる成果を共有し、現場のモチベーションを高めることも非常に重要です。あわせてカリキュラムに盛り込んでおきましょう。
一般ユーザーと活用スタイルが異なるマネージャーには、別途管理者向けトレーニングを設けることをおすすめします。営業担当者とマネージャーの双方がSFAを使いこなせなければ、蓄積したデータの効率的な活用が実現できないためです。
トレーニング終了直後は、ログイン方法や操作方法などに対する質問が急増することが予想されます。迅速かつ手厚いサポートが必要な時期なので、システム管理者のリソースを調整しておきましょう。
SFA(営業支援システム)の定着
現場がSFAのオペレーションに慣れないうちは、業務負荷の増加によって営業担当者のストレスが溜まりやすくなります。SFA活用のモチベーションを保つためにも、発生した不満や疑問に対処できる社内ヘルプデスクを設置することが有効です。
さらに、営業担当者が毎日SFAに触れられるよう、プロジェクトリーダーやマネージャーは声掛けやフィードバックを欠かさずに行いましょう。マネジメント層が率先して活用することで、SFAの意義を伝える際の説得力が生まれることに加え、運用における課題をいち早く見つけることができます。
導入後の取り組み方次第で、社内にSFAを浸透させられるか、システムが形骸化してしまうかが決まるといっても過言ではありません。導入後は四半期ごとを目安に効果測定を行い、プロセス改善を繰り返すことでSFAを完全に定着させましょう。
SFA導入で効果はある?導入事例紹介
以下では、SFAの導入事例を3社分紹介します。「SFAの導入を検討しているが、効果があるのか不安」という方は、各社の成果や導入時の工夫などをぜひ参考にしてください。
Leverages「営業現場の工数削減と顧客関係強化を同時に実現」

出典:レバレジーズ株式会社
人材系サービスをはじめ、30以上のサービスを展開するレバレジーズ株式会社は、顧客との関係を構築しやすい環境を整えるべくCRM/SFAを導入しました。

現場の営業担当者からは「タスクのフォーマットが統一されたことで他メンバーへの引き継ぎがスムーズになった」「他事業部の営業状況を簡単に確認できるようになった」などの意見が挙がっており、顧客関係を強化する基盤が整ったことが伺えます。
「複数のスプレッドシートにアクセスする手間がなくなり、作業が効率化した」との声もあり、SFAの導入が現場のプラスになることが証明された事例です。
アイダ設計「反響対応の迅速化と失注案件リサイクルで成約率が向上」

出典:株式会社アイダ設計
株式会社アイダ設計は、「心をこめた家づくり」で年間2,000棟以上の設計実績を誇るハウスメーカーです。属人的な営業からの脱却を目指し、情報基盤の見直しを図るべくSFAを導入しました。

導入当初は営業現場から強い反発を受けた当社。まずは、営業活動報告をSFAに一本化する運用ルールを整備しました。さらにトップ役員を巻き込み、営業担当者の受注報告に対して即座に役員がレスポンスを行うことで、SFAの利用を一気に定着させたといいます。
SFAでの情報管理を徹底することで、営業活動の属人性が解消され、ひいては成約率の向上につながった事例です。
参照元:Salesforce「お客様事例|株式会社アイダ設計」
森定興商「旧体質な組織における営業改革をSFA導入で実現」

出典:森定興商株式会社
森定興商株式会社は、水道管やガス管などのパイプ・鉄鋼・住宅用建材をメインに扱う総合商社です。今後のビジネス成長を図るうえで「組織営業」の取り組みが不可欠だと感じ、営業情報共有を促進すべくSFAを導入しました。

SFAの導入に際して現場の反発を予想した当社は、一部の支店から導入を開始。成功モデルを構築したうえで、徐々に全国へ水平展開する方式を採用しました。さらに、キックオフミーティング時にはSFAの必要性を現場へ訴えることに注力し、旧体質からの脱却を実現しています。
現場への影響を考慮しスモールスタートで導入したこと、現場へ導入の背景と目的についての十分な意識づけを行ったことが、SFAの定着を成功させたポイントだといえます。
参照元:eセールスマネージャー「導入事例|森定興商株式会社」
よく使われるSFA(営業支援システム)の紹介
現代では多くのベンダーがSFAを提供しているため、「どのツールが自社に適しているのだろう」と迷ってしまう方も少なくありません。
以下では、国内のSFA市場において特に導入実績の多い5つのツールをピックアップしています。特徴や費用などを紹介するため、ツール選定の参考材料にしていただけますと幸いです。
Salesforce「Sales Cloud」

出典:Salesforce
「Sales Cloud」は、世界中で高いシェアを誇るSalesforce社のSFAです。汎用性・カスタマイズ性の高さが特徴で、自社の課題にあわせて柔軟にシステムを最適化できます。
非常に多機能なツールなので、大規模な組織にはもちろん、独自の商慣習や業務ルールのある企業にも最適です。その反面、シンプルなSFAを求めている組織には過剰性能に感じられる可能性があります。
Sales Cloudを十分に組織へ適応させるには、カスタマイズやヘルプデスクを一任できる人材を自社内に配置することが望ましいです。導入・活用のハードルが高いツールなので、ITに精通した専任者がいない場合はベンダーの提供する有料サポートの利用を検討しましょう。

HubSpot「Sales Hub」

出典:HubSpot
「Sales Hub」は、営業活動を合理化し、チームの生産性向上を支援するHubSpot社のSFAです。HubSpotはマーケティング、営業、カスタマーサポート向けのソフトウェアがCRMプラットフォームに集約されており、50種類以上の基本機能が永久無料で利用できます。
「まずは無料版から始めてみよう」というスモールスタートが可能なので、ツールの導入が初めての組織においてもリスクを最小限に抑えて運用できるでしょう。
また、HubSpotのプラットフォームはゼロからHubSpot社が自社開発しているため、すべての製品群のUIが統一されています。組織の成長にあわせてツールや機能を追加する際も、使い勝手が変化しないためスムーズな導入を実現可能です。

ソフトブレーン「eセールスマネージャー」

出典:eセールスマネージャー
「eセールスマネージャー」は、ソフトブレーン社が提供する純国産のSFAです。日本の営業シーンにあわせて開発されているため、導入・活用に際して営業現場のストレスを軽減できます。
SFAの多くは海外製品のため、ツールやマニュアルの日本語翻訳には不自然な部分が少なくありません。その点、eセールスマネージャーは日本人に最適化されており、現場がツールに慣れるまでの時間を短縮できます。
オーソドックスなSFAの機能が過不足なく搭載されているため、「Sales Cloudほどの多機能は求めていない」という組織に最適です。

Microsoft「Dynamics 365 Sales」

出典:Microsoft
Dynamics 365 Salesは、Microsoft.comが提供するビジネスアプリケーションパッケージ「Dynamics 365」に搭載されているCRM/SFAです。OfficeやOutlookなどとシームレスに連携できるため、Microsoft製品を活用している組織では導入がスムーズに進むでしょう。
多機能で拡張性が高いことから、大規模な組織における導入割合が高いことが特徴です。「自社の業務プロセスにあわせてSFAを柔軟にカスタマイズしたい」と考えている中堅~大企業に適したツールだといえます。

Zoho 「Zoho CRM」

出典:Zoho
Zoho CRMは、世界で25万社の導入実績があるSFA/CRMです。月額費用が低価格なことに加え、初期費用やオプション料金も必要ないため、小規模ビジネスや低リスクで導入を検討したい組織に適しています。
一方で、日本における導入実績は比較的少なく、マニュアルやコミュニティを活用した課題解決のハードルがやや高いという側面もあります。ある程度の英語力やITリテラシーのある組織では、導入をスムーズに進められるでしょう。

まとめ
SFA(営業支援システム)は、営業活動管理機能や案件・商談管理機能、売り上げ予測機能などが搭載されているツールです。営業活動を可視化し、データの管理・分析工数を削減できることから、営業部門の生産性向上に大きく貢献します。
SFAの効果を十分に発揮させるためには、社内への浸透を第一に考える必要があります。「導入して終わり」ではなく、営業現場が日々ストレスなく活用できる運用体制を構築することが重要です。
まずはSFA導入の事前準備を十分に整えたうえで、自社にマッチしたツールを検討しましょう。本記事で紹介した失敗を避けるポイントや導入手順、企業の成功事例などを参考に、SFAによる営業改革を成功に導いていただけますと幸いです。
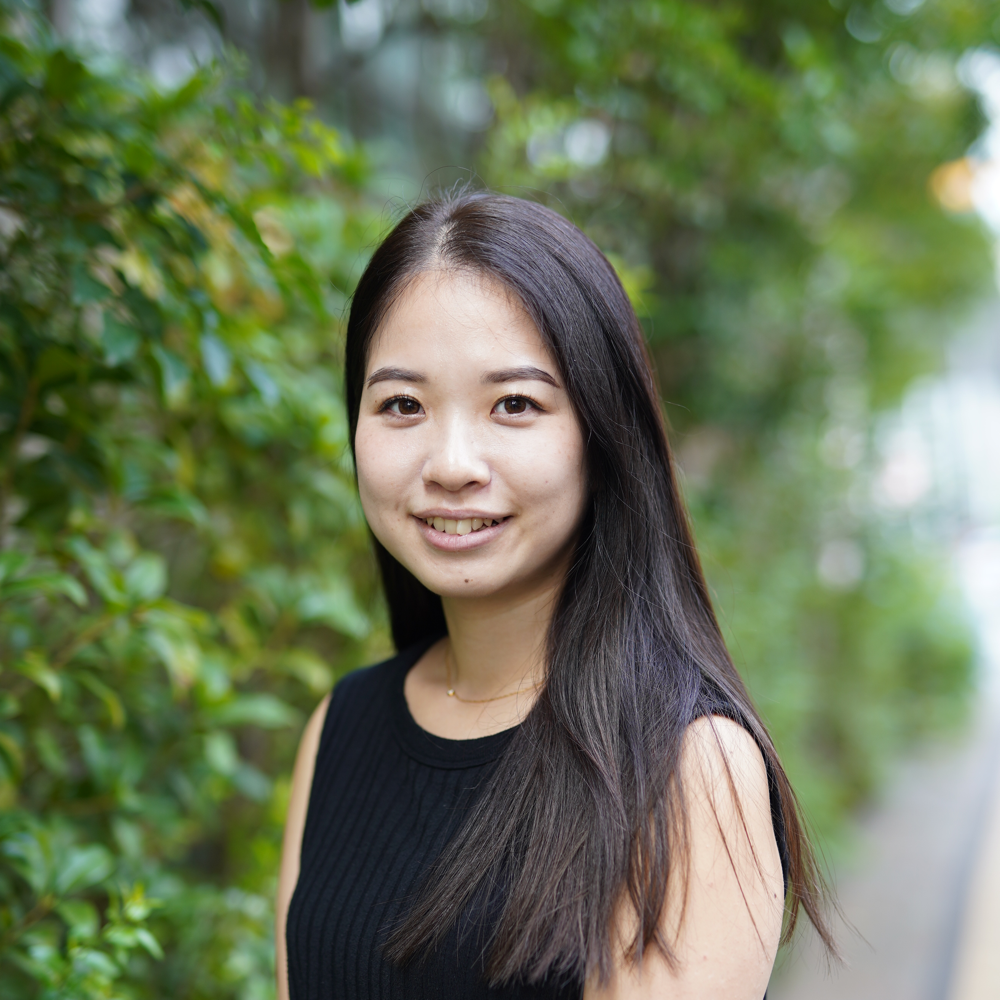
渋谷 真生子
株式会社100(ハンドレッド)のマーケター。新卒でグローバルヘルスケア企業で営業を経験し、セールスフォースにてBDRとして地方企業の新規開拓に携わる。コロナ渦でインバウンドマーケティングの重要性を実感し、アイルランド ダブリンにあるトリニティカレッジの大学院にてデジタルマーケティングの学位取得し現在に至る。最近はかぎ針編みにハマり中。
We are HubSpot LOVERS
ビジネスの成長プラットフォームとしての魅力はもちろん、
HubSpotのインバウンドマーケティングという考え方、
顧客に対する心の寄せ方、ゆるぎなく、そしてやわらかい哲学。
そのすべてに惹かれて、HubSpotのパートナー、
エキスパートとして取り組んでいます。
HubSpotのこと、マーケティング設計・運用、
組織の構築など、どんなことでもお問い合わせください。