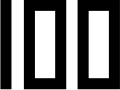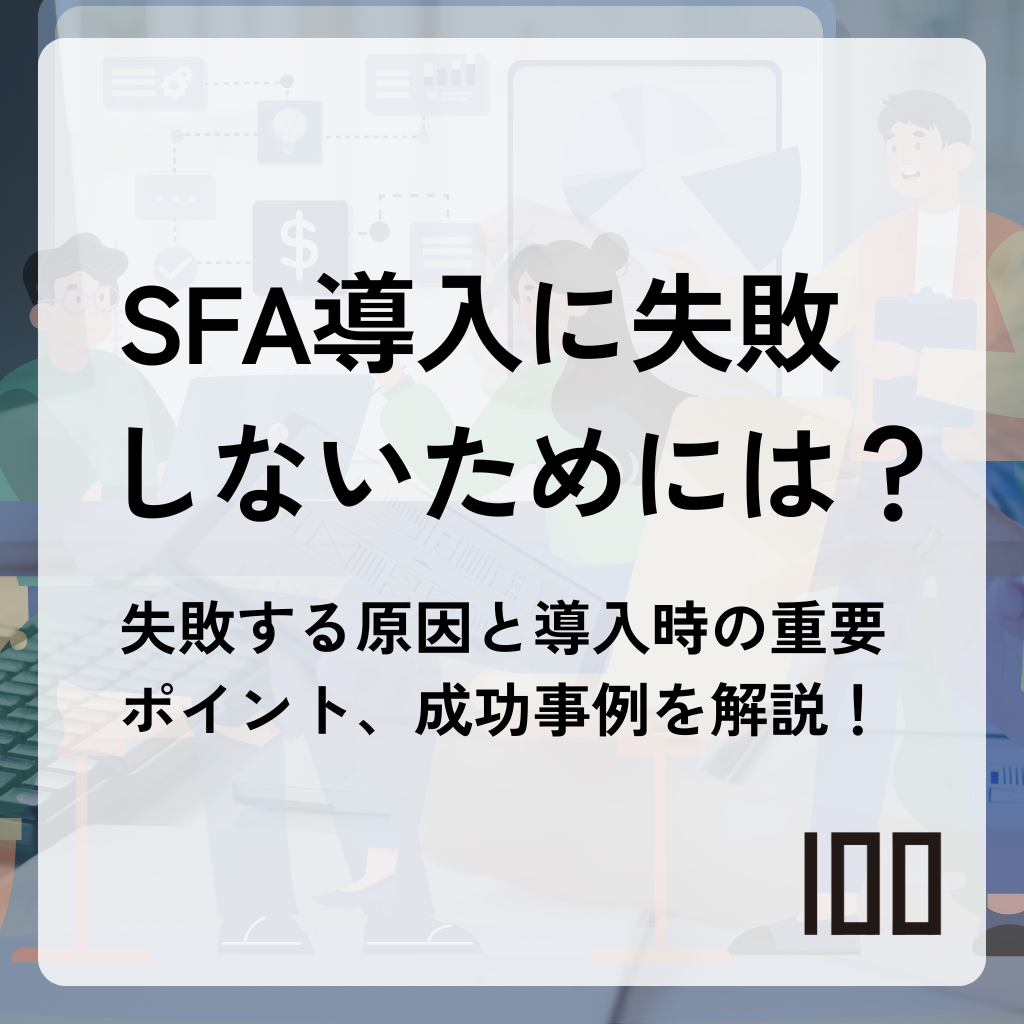

SFA(営業支援システム)は、顧客情報や営業プロセスの管理・共有により、営業効率を向上させるためのシステムです。活用することで、各営業担当者の業務を見える化することや、営業活動の標準化などに役立ちます。
しかし、営業効率の改善を目指してSFAを導入したものの、現場で定着せず使われなくなるといった失敗例も少なくありません。
2023年4月に日本オラクルが実施した「SFA/CRMの導入・利用状況に関するアンケート調査」では、経営・経営管理部門がSFAやCRMに期待する効果が「収益性向上(48%)」であるのに対し、実際に「達成している」と回答したのは25%でした。期待と現実の間に大きなギャップがあることが明らかになっています。
SFA導入の失敗にはさまざまな原因が潜んでおり、うまく活用されなければSFAシステムは本来の効果を発揮できません。
本記事では、SFA導入でよくある失敗の原因と失敗を防ぐためのポイント、SFA導入に成功した事例について解説します。
SFAとは?をおさらい
まずは、SFAの基礎を再確認しておきましょう。ここでは、SFAの概要と国内導入率をまとめた上で、今後の日本でSFAを活用した営業DXが重要といわれている理由についても解説します。
SFA(Sales Force Automation)とは?
SFAとは「Sales Force Automation」の略称であり、企業の営業部門における営業活動をデータとして蓄積・分析できるシステムです。日本語では「営業支援システム」と呼ばれ、以下のような営業活動に役立つ機能が搭載されています。
【SFAの主な機能】

このような機能をもつSFAを導入することのメリットは、営業活動の可視化と効率化ができることです。これにより、以下のような課題を解決できます。
- 効果的な営業戦略の立案
- 営業上の課題の早期発見
- 問題発生時の迅速な対応
- スムーズな引き継ぎ
- 関連部署間での営業情報の円滑な共有
- 営業業務の属人化防止
SFAは、特に営業リソースが限られた中小企業において大きな効果を発揮します。
クラウド型のSFAを導入することで、インターネット環境さえあればどこからでもアクセス可能になり、営業情報をリアルタイムで共有できます。これにより、チーム全体のパフォーマンス向上と、業務の効率化・生産性向上が期待できます。
さらに、SFA上で日報や週報の作成・共有できるため、メールでの報告送付の手間を省き、ワークフロー管理の効率化にも寄与します。
【関連記事】
・【基礎徹底解説】SFA(営業支援システム)とは?CRM・MAとの違いやおすすめツールまで紹介!
SFAの国内導入率
株式会社TSUIDEが実施した「SFA、CRM導入実態に関する調査」によると、日本国内のSFA/CRMツールの導入率は9.1%に留まっており、約90%が未導入の状況です。この結果から、日本におけるSFAツールの普及率は依然として低いことが分かります。
しかし、IDC Japan株式会社が発表した「国内パブリッククラウドサービス市場予測、2024年~2028年」の調査レポートによると、日本国内のSFA市場はこれまで年率約10%の堅実な成長を続けており、2024年以降は急速な拡大が見込まれています。
また、MarkWide Researchの調査レポートでは、世界のSFA市場は2023年から2030年の間に年平均成長率(CAGR)は18.7%で拡大していると示されています。2023年の273.55億ドル(2023年現在の為替レートで約3兆9343億円)から、2030年には908.21億ドル(約13兆593億円)に達するとされており、この勢いは今後も衰えないと予測されています。
今後の日本でSFAを活用した営業DXが重要な理由
日本企業の営業分野では、SFAを活用した営業DXの重要性が増しています。SFA市場の成長を促進している主な要因として、次の5つが挙げられます。
- 政府のデジタル化推進
- 企業のDX投資の増加
- リモートワークの普及
- 顧客の購買行動の変化
- 労働生産性向上へのニーズの高まり
一つは、政府がデジタル化を推進していることです。DX(デジタルトランスフォーメーション)の取組状況を業種別に見ると、情報通信業がもっとも進んでおり、約45%の企業がすでに取り組んでいると回答しています。また、製造業、エネルギー・インフラ、商業・流通業はそれぞれ約25%の企業が実施しています。

引用:令和3年版 情報通信白書|我が国におけるデジタル化の取組状況|総務省
政府のデジタル化推進を受け、多くの企業が業務効率化や競争力強化を目指して投資を増加させており、その一環としてデジタルツールの導入、特にSFAの導入が加速していると考えられます。
また、リモートワークの普及もSFAの需要が高まる要因の一つとなっています。SFAを導入することで、リモート環境でも営業情報の共有や進捗管理が可能になり、営業活動を効率的に進めやすくなります。
顧客の購買行動が多様化・デジタル化する中で、企業は顧客との接点を強化し、的確なアプローチをすることが求められるようになっています。SFAは顧客データを一元管理し、データに基づいた営業活動を実施できます。
さらに、SFAは営業プロセスの標準化を支援し、組織全体での営業力向上に貢献します。営業活動を標準化することで、個々の営業担当者に依存せず、安定したパフォーマンスを発揮することが可能です。
労働生産性を向上させるニーズが高まる中、SFAは効率的に営業活動を行うためのツールとしての重要性が増しています。SFAを活用することで、手作業や重複業務の削減が可能になり、生産性の向上につながります。
SFA導入に失敗した理由とは?
SFAの導入は、多くの企業にとって営業活動の効率化や生産性の向上を目指す重要な施策の一つです。しかし、SFAの導入が必ずしも成功するわけではなく、多くの企業がその効果を十分に発揮できずに導入を断念するケースも少なくありません。
アイティクラウド株式会社が実施した「DX推進に関する実態調査2022」によると、67.4%の経営者が過去にSaaS製品の導入に失敗した経験があると回答しています。そのうち「何度もある」が29.8%、「1〜2回程度ある」が37.6%という結果でした。
SFA導入に失敗した原因を理解することで、成功への道筋が見えてくるはずです。ここでは、SFA導入が失敗する主な理由を6つ挙げて解説します。
SFAが使われない!営業からの拒否反応
SFAの導入においてもっとも多い失敗理由の一つが、現場の営業担当者による拒否反応です。営業現場では日々の業務の中ですでに確立されたやり方があるため、そこに新たなシステムを導入することに対する拒否反応が起こりやすい環境といえます。
新しいツールの使い方を覚える手間や、従来の方法からの変更を強いられることへの不満から、営業担当者がSFAの使用を避ける傾向があります。
株式会社TSUIDEが実施した「SFA、CRM導入実態に関する調査」によると、「ツールを効率的に活用できていますか?」という質問に対し、「導入している」と回答した企業のうち、「ツールを効率的に活用できている」と答えたのは73%でした。
一方で、「活用できていない」と答えた企業が27%に上り、ツール導入後の効果的な活用が課題となっている現状が浮き彫りになっています。

引用:SFA、CRMツール導入に関する調査結果|株式会社TSUIDEのプレスリリース|PR TIMES
具体的な拒否反応の原因として、SFAの操作が複雑で使いにくいと感じることや、データの入力作業が増えてしまい、実際の営業活動に割ける時間が減ってしまうという懸念があります。また、日常的な業務に追われる中で、新しいシステムを使いこなすための研修やトレーニングに時間を割く余裕がないという事情もあるでしょう。
こうした理由から、SFAが導入されても現場で使われず、結果的に導入が失敗に終わることが多いと考えられます。
社内の従来の営業文化が変わらず、そのままシステムだけを導入した場合、SFAに対する拒否反応が発生することがあるため、SFAの導入前に営業部門がそのメリットを理解し、システムの活用方法を確実に把握することが重要です。
経営陣や営業マネージャーのリーダーシップ不足
SFAの導入を成功させるためには、経営陣や営業マネージャーの強いリーダーシップが不可欠です。しかし、経営陣や管理職がSFA導入の重要性を十分に理解しておらず、積極的に推進する姿勢が見られない場合、導入プロセス全体がうまく進まないことがあります。
株式会社Merが実施した「SFAを導入している企業の管理と現場の比較調査」では、「営業担当者がSFAに顧客情報や商談情報を漏れなく正確に入力できていると思いますか?」という質問に対し、「できている」と回答したのは、部長・課長では27.1%、営業担当者では12.7%であり、両者の間には14.4ポイントの差があることが示されました。

引用:SFAを導入している企業の管理と現場の比較調査 | 株式会社Merのプレスリリース|PR TIMES
経営陣やマネージャーがSFAの導入に積極的に関わらず、現場任せにしてしまうと、導入目的や目標が曖昧なまま進行し、営業チームがシステムをうまく活用できないままになってしまいます。
また、リーダーシップの不足は、営業チームに対する指示の不徹底や、SFAを活用した営業活動の効果を共有する機会の欠如につながり、現場のモチベーションを低下させる恐れもあります。
上層部が主要な決定権を持ち、組織全体に対して指示を下す(トップダウンでのガバナンス)ことで、組織の統制や戦略的な方向性を維持しやすくなります。
導入後の運用体制が構築されていない
SFAは導入して終わりではなく、その後の運用体制の整備が重要です。導入時のシステム運用担当者や運用方法、またトラブルが発生した際の対応方法、さらにはシステムを改善していくための体制が整っていない場合、SFAがうまく機能しない要因となります。
例えば、データの入力ルールが明確に決まっておらず、担当者ごとに入力内容やフォーマットが異なり、データの一貫性が保てなくなる可能性があります。また、システムの管理者が不在の場合、SFAの運用に関する問い合わせ対応やトラブルシューティングが滞り、システムの信頼性が低下することもあるでしょう。その結果、現場での利用が進まなくなるといった悪循環に陥ってしまいます。
導入後に責任者や運用体制、運用ルールが決まっておらず、SFAが見切り発車で導入された結果、社内に推進担当者がいないために結局使われずに終わってしまうことがあります。
SFAを成功に導くためには、継続的に啓蒙活動を行う担当者の存在が不可欠です。
SFAの構築が自社の営業プロセスにカスタマイズされていない
SFAを効果的に活用するためには、企業ごとの営業プロセスに合わせてカスタマイズすることが必要ですが、これが適切に行われていないと、現場にそぐわないシステムとして機能不全に陥ることがあります。
自社の営業プロセスや文化に合わない設定や機能が多いと、営業担当者はそのツールを使うことに負担を感じ、活用されなくなる恐れがあります。
株式会社Merの同調査では、「営業担当者が商談後すぐにSFAに顧客情報や商談情報を入力できていると思いますか?」という質問に対し、部長・課長の23.5%が「できている」と回答しましたが、営業担当者ではその割合が1割に満たない結果でした。
顧客情報や商談情報が正確に、または商談後すぐに入力されない理由として、「複数の機能を活用しており、入力項目が多いため」がもっとも多く挙げられています。

引用:SFAを導入している企業の管理と現場の比較調査 | 株式会社Merのプレスリリース|PR TIMES
例えば、自社特有の商談プロセスや営業フローに対応していないシステムは、営業担当者にとって使いづらく、業務の流れを妨げる要因となるでしょう。
また、デフォルトの設定や画面が複雑であったり、使い勝手が悪かったりすると、営業チームがシステムを敬遠する原因にもなり得ます。その結果、導入後も旧来の方法に戻ってしまい、SFAが形骸化してしまうことがあります。
自社にあったツールを選定できなかった....!
SFA導入に失敗する理由として、自社のニーズに合ったツールを選定できなかったことも挙げられます。
市場には多くのSFAツールが存在し、それぞれに特徴や機能が異なります。自社の営業スタイルや規模、業界特性に適したツールを選ばなければ、導入後に期待通りの効果を得られない可能性があります。
例えば、大企業向けの多機能なSFAを導入したものの、中小企業には機能が過剰で使いこなせないかもしれません。逆に、小規模向けのシンプルなツールを選んでしまい、必要な機能が不足するケースもあります。
また、選定段階で現場の営業担当者の意見を十分に反映せず、実際の業務と乖離したシステムを選んでしまうこともあります。このような場合、導入後にシステムの変更や再導入が必要になり、余計なコストと時間を費やす結果となってしまうでしょう。
導入目的や目標が曖昧で統一されていない
SFA導入の失敗は、導入の目的や目標が明確でないことにも起因します。導入の目的や達成したい目標が曖昧なままでは、必要な機能やデータが不明確となり、システム導入後に改善点や効果を把握することが難しくなり、結果的に導入効果が見えにくくなります。
例えば、営業効率の向上を目的にSFAを導入した場合も、具体的な目標設定がされていないと、営業チームがどの基準で活動を進めるべきかが不明確になります。
これにより、SFAの導入が業務の負担を増やすだけになってしまい、効果が実感できないという事態に陥ることがあります。
SFA導入に失敗しないためのポイントは?
SFAを導入する際にはさまざまな課題があり、適切に対処しなければ失敗に終わる可能性もあります。ここでは、SFA導入を成功させるための10のポイントをご紹介し、各ステップでの実践方法について詳しく解説します。
無料トライアルやデモを最大限に活用する
SFAの導入後に、「実際に使用したら使いにくい」「必要な機能がなかった」とならないためにも、本導入の前にまずは無料トライアルやデモを活用することがポイントです。これにより、システムが実際にどのように機能するかを確認でき、導入後のミスマッチを防ぐことができます。
無料トライアルやデモでは、営業管理・顧客管理・レポート作成など、必要な機能がそろっているかをチェックしましょう。
また、システムのユーザーインターフェース(UI)が使いやすいかどうかも重要なポイントです。実際に操作してみることで、直感的に使えるか、複雑な操作が必要かどうかを試すことができます。
導入後には自社の営業プロセスに合わせてシステムを変更する必要があるため、どれだけカスタマイズ可能かといった柔軟性も確認しておくと良いでしょう。
他にも、トライアル中に発生する疑問や問題について、迅速かつ丁寧にサポートが受けられるかどうかも判断材料となるでしょう。
SFAの無料ツールの例)Sales Hub | HubSpot

スモールスタートする
SFAを全社的に一度に導入するのはリスクが高いことから、まずは限定的に導入してから全体に展開する「スモールスタート」のアプローチが推奨されます。営業所を多く展開している場合、はじめからすべての営業所に導入するなどは避け、まずは抵抗感の少ない営業所や部門で試験的に導入すると良いでしょう。
その際に、システムの操作感や効果を実際の業務で確認し、問題点を洗い出しておきます。
試験導入で得たデータや現場担当者からのフィードバックをもとに、問題点を改善しながら段階的に全社展開を進めることで、リスクを最小限に抑えながら効果的な導入が可能になります。
経営陣、営業マネージャーのリーダーシップを発揮する
SFA導入は単なるシステムの導入ではなく、組織全体の営業プロセスを変革する取り組みです。そのため、導入の成功には、経営陣や営業マネージャーの強力なリーダーシップが欠かせません。
経営陣が積極的にプロジェクトに関与し、プロジェクトの重要性を全社に伝えることで、導入に対する理解と協力を得やすくなります。
具体的には、SFAの活用方法やメリットについて、営業担当者への啓蒙活動を積極的に実施するといった方法があります。定期的なミーティングやセミナーを通じて、システムの理解を深めることが重要です。また、成功事例やシステムの効果を定期的に共有することで、全社的なモチベーションを高められます。
SFA運用責任者を設ける
SFAが効果的に活用されない主な理由として、運用担当者がおらず利用が推進されないことが挙げられます。そのため、SFA導入に失敗しないためには、運用責任者を設定することが重要です。営業担当者が疑問や問題に直面した際に相談できる専任の担当者がいることで、SFAの導入と運用が円滑に進むことが期待できます。
SFA運用責任者の役割は、SFAの効果的な導入と運用を支えるポジションであり、具体的な役割と業務には、以下のようなものが挙げられます。

SFA運用責任者がこれらの役割を適切に果たすことで、SFAの導入と運用がスムーズに進み、システムの効果を最大限に引き出すことが可能です。
実際に、SFA運用責任者を導入して成功を収めた事例として、明和工業株式会社が挙げられます。同社ではSalesforceの導入時に、社内にITに詳しい人材が不足していたことから、外部からSalesforce専任の担当者を新たに採用したといいます。
担当者は、利用定着化のために、例えばSales Cloudの日報に入力漏れがあるとデータが保存できないように設定したり、IT用語を社員にとって理解しやすい言葉に置き換えたりするなど、多くの工夫を行ったそうです。
短期間で導入と運用を支える重要な役割を果たすようになり、結果として、営業担当者のデータ入力への意識が向上し、SFAの活用が進んだという成功事例です。
入力項目はできるだけシンプルに
SFAの入力項目が多すぎると現場で使われずに導入に失敗するケースが多いことから、入力項目はできるだけシンプルにすることが求められます。
株式会社Merの調査によると、「現在利用しているSFAが使いづらい」と感じる理由として、以下の点が挙げられました。

引用:SFAを導入している企業の管理と現場の比較調査 | 株式会社Merのプレスリリース|PRTIMES
「入力項目が多すぎる」と回答した割合が55.3%で、「直感的に操作できる画面へのカスタマイズができない」とした割合が55.2%となっています。また、「入力形式が選択肢ではなくテキスト入力が多い」と「業務内容に合わない」といった意見も寄せられていました。
本当に必要な入力項目を慎重に検討し、営業活動に直接関係する情報のみを入力項目として設定しましょう。導入後も定期的に見直し、営業担当者のフィードバックをもとに改善を続けることがポイントです。
SFA入力をしないと商談を進めることができないようにする
SFAで正確な分析や予測を行うためには、統一された内容やフォーマットで一定数のデータを蓄積していく必要があります。SFAの使用率改善には、商談の進行にSFAの入力を必須条件とすることが有効です。
例えば、商談のステージごとに必要な情報をSFAに入力しなければ次のステップに進めないよう設定します。
また、入力漏れや不完全なデータを防ぐために、自動化されたリマインダー機能やチェック機能を活用することもおすすめです。これにより、入力漏れや遅延を早期に発見し対応しやすくなります。
必要な場合はSFA入力にインセンティブを設ける
SFAの利用促進を図るために、入力に対してインセンティブを設け、営業担当者のモチベーションを高めることも一つの方法です。
具体的には、SFAへの入力に対してポイント制度や報奨制度を導入し、入力が徹底されている営業担当者に対して報酬を提供するといった方法があります。報酬例としては、月間の入力データ数に応じたボーナスや商品券などが挙げられます。
さらに、チームの営業担当者が全員、1年間データ入力を漏れなく行った場合には、金一封が贈られるというインセンティブを設定する企業もあります。こうした取り組みにより、データ入力の重要性が認識され、SFAの活用が進むでしょう。
社内の教育を実施する
SFA導入に失敗しないためのポイントとして、導入後に社内教育を徹底的に実施することも挙げられます。システムの使い方や活用方法についての研修を行い、営業担当者や管理者に正しい操作方法を理解してもらう必要があります。
株式会社TSUIDEが行った「SFA、CRM導入実態に関する調査」では、導入したSFAやCRMツールが「活用できていない」と回答した人へ理由を尋ねたところ、「使い方・操作が難しい」と「機能を使いこなせない」の2点が全体の約半数を占める結果となりました。
この調査から、デジタルツールは導入されているものの、ツールの有効活用に必要な知識が不足しており、効率的に活用できていない現状が明らかになっています。

引用:SFA、CRMツール導入に関する調査結果|株式会社TSUIDEのプレスリリース|PR TIMES
対策として、オンライン研修や対面研修を組み合わせ、定期的なトレーニングを実施し、新機能の追加やシステムのアップデートにも対応できるようにする必要があります。また、教育後のサポート体制も強化し、継続的なサポートを提供することで、SFAの効果を最大限に引き出すことができます。
SFA導入プロジェクトに営業担当者を加える
SFA導入は、チームのリーダーが率先しトップダウン型で進めることが重要ですが、導入プロジェクトには、営業担当者を加えることもポイントです。
営業担当者がプロジェクトチームに参加することで、現場のリアルな課題や業務フローを正確に把握できます。
さらに、営業担当者がプロジェクトチームに参加することで、導入後のトレーニングやサポートもより効果的に進めやすくなるでしょう。彼らがシステムの使い方や利点を熟知することで、他の担当者に対しても指導や支援を行うことができ、全体のスムーズな運用が期待できます。
導入後の効果検証を実施する
SFAの導入後には、効果検証を実施することが欠かせません。効果検証を通じて、SFAの導入が実際に営業業務にどのような影響を与えているかを把握し、必要に応じて調整や改善を行うことができます。
例えば、営業の成約率・業務効率・顧客満足度などの指標を定量的に測定し、導入前と後での変化を分析すると良いでしょう。これにより、SFAが実際に業務改善に寄与しているかどうかを評価できます。
また、効果検証の結果に基づき、必要な改善策を講じることが求められます。具体的には、システムの機能追加やカスタマイズ、ユーザーインターフェースの改善などが考えられます。
定期的なレビューやアップデートを行い、SFAが常に最適な状態で運用されることを目指しましょう。
他ツールと連携して効果を高める
SFAは営業活動を効率化するための強力なツールですが、他のシステムやアプリケーションと連携することで、さらに高い効果を得ることができます。
例えば、CRM(顧客関係管理)システムとの連携が挙げられます。
CRMは顧客情報管理のためのツールであり、SFAとの統合により、顧客データをリアルタイムで共有することが可能になります。
これにより、営業担当者は顧客の履歴や状態を把握しやすくなり、より効果的な営業戦略を立てることができます。
また、MA(マーケティングオートメーション)ツールとの統合も効果的です。MAツールはマーケティング活動の自動化を支援するツールであり、リードジェネレーションやキャンペーン管理などを行うことが可能です。
SFAとMAツールを連携させることで、マーケティング活動と営業活動の連携が強化され、リードの質やコンバージョン率の向上が期待できます。
実際に、株式会社Merの調査によると、導入しているSaaSツールのうち、他ツールと連携している割合を尋ねた結果、回答者の29.1%が「5割〜6割程度」と回答し、24.0%が「7割〜8割程度」、3.8%が「9割以上」と答えています。このことから、SaaSツールと他ツールを5割以上連携して活用している人は、全体の約6割いることが分かります。

引用:SFAを導入している米国企業の管理と現場の比較調査 | 株式会社Merのプレスリリース|PR TIMES
SFAは単体での利用よりも、他ツールと連携することでさらに営業活動の効率化と成果向上を実現できるため、他システムとの連携を積極的に検討することが重要です。
SFA導入に成功した事例紹介
SFAの導入によって、多くの企業が営業活動の効率化や業務の改善を実現しています。これらの成功事例から学ぶことで、SFAの導入における具体的な成功要因を把握し、自社に適した導入戦略を立てやすくなるでしょう。
ここでは、SFAを効果的に活用し成果を上げた企業の成功事例を3社ご紹介します。
株式会社レバレジーズ:HubSpotの「Sales Hub」で営業効率化と連携強化

引用:レバレジーズ
インターネットメディア・人材・システムエンジニアリング・M&A事業を展開するレバレジーズ株式会社では、HubSpotの「Sales Hub」を導入し、顧客関係構築のための環境整備を実現しています。
30以上のサービスを展開する同社は、SFA導入前には各事業部で顧客情報や営業進捗を管理していたことから、同一の見込み客に対して異なる事業部から重複したアプローチが行われており、コミュニケーションの不一致が生じていたといいます。
また、顧客情報や営業進捗は複数のスプレッドシートで管理されており、事業の拡大に伴い管理作業が増加していたそうです。
はじめてSFAを導入するにあたり、最低限必要な機能に絞り、顧客情報の一元管理と営業メンバーのタスク、リード、営業進捗状況の統合管理を必須条件と設定しました。
具体的には、レバレジーズの人材系3サービス(ハタラクティブ、キャリアチケット、他1サービス)にHubSpot CRMとSales Hubを導入し、営業メンバーのタスクやアクティビティ管理の統一を進めたといいます。これにより、マネジメントの管理効率化と営業メンバーの業務効率化が実現しています。
また、顧客ごとのステータスが明確になり、アプローチの方針が判断しやすくなったことから、営業メンバーからは、「タスクのフォーマットが統一され、他のメンバーとの共有がスムーズになった」「他事業部のアプローチ状況が簡単に確認できる」「これまで複数のスプレッドシートで確認作業をしていたが、一つに集約されて作業が楽になった」といった喜びの声が上がっているとのことです。
同社ではその後、Marketing Hubも導入し、マーケティングチームとの連携を強化することで、より適切な顧客コミュニケーション環境の整備を進めているそうです。
GLナビゲーション株式会社:Salesforceで営業DXを加速

引用:GLナビゲーション
人材育成サービスとDXコンサルティングを提供するGLナビゲーション株式会社は、コロナ禍による売上低迷を契機に営業のDX化を進める目的から、営業組織とプロセスの改革を行い、Salesforceを内製で導入することを決定しました。
以前の営業スタイルでは、営業担当者がアポ取りから顧客フォローまですべてを一人で行い、顧客や商談の情報はExcelやホワイトボードで管理していたそうです。そのため、担当者が退職すると情報が失われ、一からやり直しになることもあり、経験と勘に頼る営業活動が行われていたといいます。
この状況を打破するために、2020年に営業DXの推進を決定。まずは、オペレーションの分業体制を整備し、各部署の役割の明確化を進め、オープンな情報共有とデータに基づく意思決定のサイクルの構築を実現しました。
次に、Salesforceを導入し、保守や運用改善を行いながら、営業全員がSalesforceを活用できるようにトレーニングを実施しました。
データ入力の問題に対しては、テキスト項目を削減しチェックボックス形式に変更、さらにインサイドセールスに入力責任を持たせるとともに、フィールドセールスが入力しない場合に代行する仕組みを導入したそうです。
リードの振り分け権限をインサイドセールスに与えることで、入力に協力的でないフィールドセールスは案件を少なくされ、自然に入力に協力するようになったといいます。
実際の担当者のコメントとして、「Salesforceに蓄積されたお客様のデータを活用することで、会話を円滑に進められます。また、データに基づいて意思決定することで、正しい方向に進んでいるという自信が持てます。」といった内容が掲載されていました。
Salesforceの導入により、以前は把握できなかった行動と数字の相関関係を詳細に分析できるようになり、因果関係を明らかにしながら意思決定が可能となっています。これにより、営業担当者1人当たりの生産性が40%向上し、新卒営業社員全員が売上1億円を突破するという成果を上げています。
出典:Salesforceの導入事例|GLナビゲーション株式会社
ワケンビーテック株式会社:Zoho CRMのSFA機能で業務効率化と情報一元管理

引用:ワケンビーテック株式会社
京都市を拠点に医療関連製品の製造・販売を行うワケンビーテック株式会社は、長年使用していた自社開発システムから、SFA機能を含むZoho CRMへの移行を決断し、顕著な成果を上げています。
同社の旧システムでは、営業活動や顧客情報、商談プロセスの管理ができず、エクセルとシステムを行き来しながら在庫や売上を確認するという非効率なオペレーションが行われていたそうです。
また、各部署が独自のシステムを運用していたため、営業部門は営業の情報のみ、サポートチームはサポートの情報のみと、部門ごとに情報が分断され、顧客情報管理の概念も欠如していたといいます。
「販売機会のロストは悪」との考えから、在庫や営業プロセス、商談プロセスの管理を可能にするシステムが必要とされており、Zoho CRMのSFA機能を導入。その後、部門ごとに独自に管理していた顧客情報が一元管理されるようになり、リードのフォローアップ、商談の進捗管理、見積書・請求書の発行など、営業活動に関連する業務の効率化を実現しています。
導入に携わった担当者は、「システムの重要性を理解し、その利用を促進するためには、単にマニュアルを提供するだけでなく、なぜこのシステムが重要なのかを伝えることが大切。」と話しており、今後はZoho CRMをさらに活用し、インサイドセールスの強化を目指していく旨を伝えています。
まとめ
SFAを導入することで営業業務の効率化が期待できますが、実際には現場で定着せず挿入に失敗する例も少なくありません。SFA導入の際には、潜在的な失敗要因を把握し、それを避けるための対策を講じることが重要です。
まずは無料トライアルを利用して営業担当者に実際に触れてもらい、現場のフィードバックを集めることが重要です。その後、スモールスタートで必要に応じて機能や利用者の範囲を拡大すると良いでしょう。
また、SFAの導入は単なるスタートに過ぎず、運用を通じて自社に最適な方法を模索し続ける必要があります。SFA選びから導入後の運用まで丁寧に対応し、導入を成功に導きましょう。
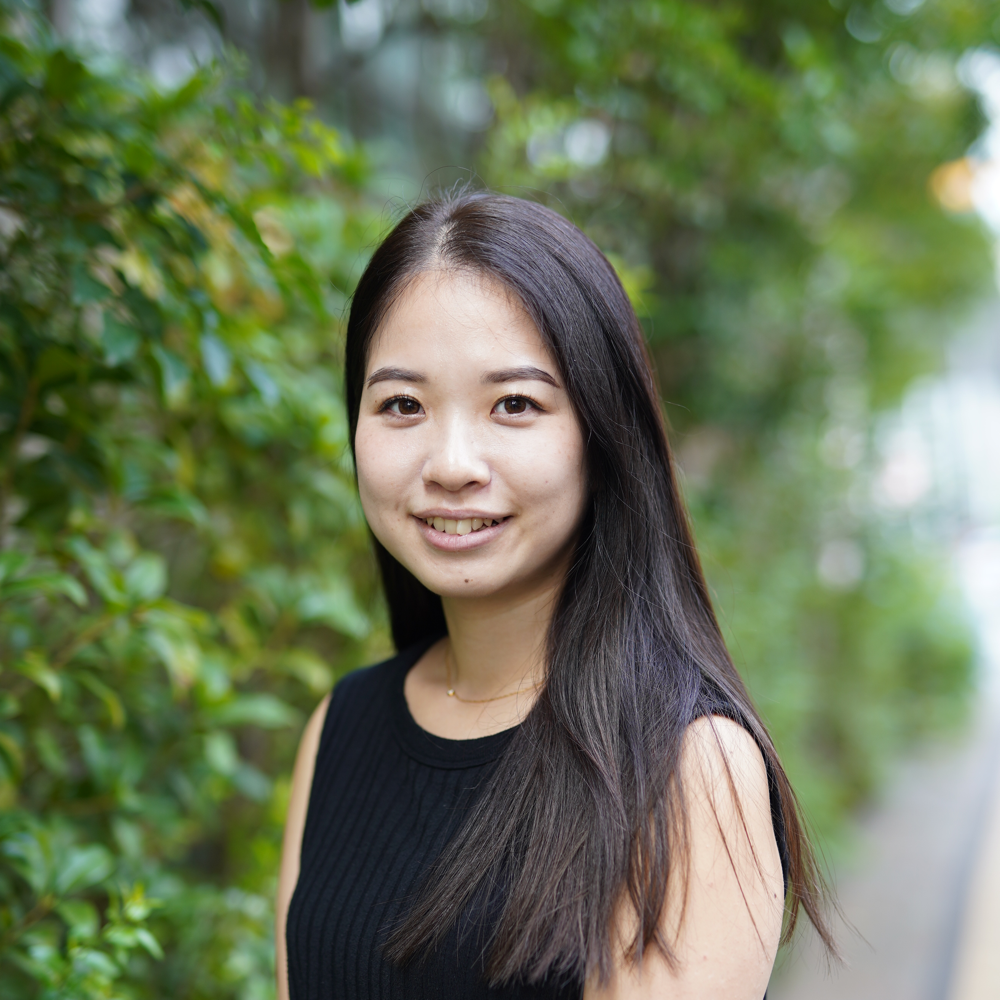
渋谷 真生子
株式会社100(ハンドレッド)のマーケター。新卒でグローバルヘルスケア企業で営業を経験し、セールスフォースにてBDRとして地方企業の新規開拓に携わる。コロナ渦でインバウンドマーケティングの重要性を実感し、アイルランド ダブリンにあるトリニティカレッジの大学院にてデジタルマーケティングの学位取得し現在に至る。最近はかぎ針編みにハマり中。
We are HubSpot LOVERS
ビジネスの成長プラットフォームとしての魅力はもちろん、
HubSpotのインバウンドマーケティングという考え方、
顧客に対する心の寄せ方、ゆるぎなく、そしてやわらかい哲学。
そのすべてに惹かれて、HubSpotのパートナー、
エキスパートとして取り組んでいます。
HubSpotのこと、マーケティング設計・運用、
組織の構築など、どんなことでもお問い合わせください。