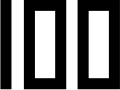HubSpot Content Hub奮闘記 AIでコンテンツ制作を効率化!―AI生成でリソース不足を脱却せよ
-3.png)

こんにちは。株式会社100(ハンドレッド) RevOps 部門の渋谷です。
このブログでは、HubSpotのContent Hubの機能を活用し、日々時間や手間がかかっている作業の効率化、新しい機能でどこまでできるのかといった検証していこうと思っています。
日々進化し新機能が追加され、UIが変化するHubSpot……。キャッチアップするのが非常に大変ですが、皆さんと一緒にHubSpotを最大限に活用していくべく勉強していけたらと思っています。
今回のテーマは、「HubSpot AIを使ったコンテンツ生成」
ご存知の通り、コンテンツ制作ってやることが多いですよね。ブログ記事作成にメルマガ配信、SNS投稿。「全部手が回らない!」というのが正直なところです。最近ではそのような業務を効率化するべく、AIを日々の業務に取り入れることが増えてきており、HubSpotもAIツールの「Breeze」を提供しています。
そこで今回は、HubSpotに搭載されているAIを使って、実際にブログ記事・メールマガジン・SNS投稿文の3種類をまるっと自動生成してみました。今現時点でのHubSpot AIでどこまでできるのかレビューしていければと思います。
現在のコンテンツ生成における弊社の課題....2つの不足とは?
コンテンツマーケティングに取り組む企業が増える一方で、「思うように成果が出ない」「継続的な発信が難しい」と感じている担当者も多いのではないでしょうか。
実際、リンクアンドパートナーズがBtoB企業のマーケティング担当者約1,000名を対象に実施した調査でも、最も多く挙がった課題は「発信するコンテンツ・ネタがない(42.1%)」、次いで「スキル・人材不足(33.8%)」でした。マーケティング業務に携わっている方なら共感できるのではないでしょうか。

(参照:リンクアンドパートナーズ調査)
このアイデア出しとリソース不足という2つの課題は、まさに私たち自身が直面している現実でもあります。弊社の公開しているコンテンツは自社で作成することもありますが、人手が足りないので多く外部の方の力もお借りしています。
ブログやメールマガジン、ウェビナー、事例作成と日々多岐にわたる制作業務に追われています。物理的な手が足りないことに加え、長く続けているがゆえに新鮮な切り口やテーマが見つかりにくくなってきたという実感も正直あります......。
そこで今回、こうした課題を打開する一手として、HubSpot生成AI機能に注目しました。限られた時間でも、質の高いコンテンツを継続的に生み出せる手応えがあるのか。実際に使ってみて、その可能性を探っていきたいと思います!
AIを活用したコンテンツ生成の基礎
コンテンツ制作に取りかかる前に、あらためてAIコンテンツ生成のメリットや注意点を整理したいと思います。
AIコンテンツ生成のメリットと可能性
AIを導入する最大のメリットは、やはり作業スピードの向上にあります。0から10を生み出すのと、7から10を仕上げるのとでは、労力も時間もまったく違いますよね。
たとえば、Emplifiが実施した調査によれば、AIを使ってコンテンツ制作をしている多くのユーザーが、「1つのコンテンツあたり最大1時間の短縮を実感している」とのこと。仮に月に10本のコンテンツを作っていたら、年間で120時間もの余裕が生まれる計算になります。
私自身も、コンテンツを作るときにこの力を借りたいと思っています。
構成を練りに練ったうえで、下書きだけでもAIに任せれば、肉付けや編集に集中できるはずです。仕上がりの質を下げることなく、考えるべきところ、たとえばSEOの構成案などに注力できるのは大きな魅力となります。
さらに、AIは情報収集にも活用できます。
生成AIは、ユーザーの関心や行動履歴に基づいて、最適な情報を提示します。これは、ネット上の情報を収集するだけでなく、HubSpotであればCRMに蓄積された顧客情報を抽出することも可能です。たとえば、AIに自社に関心を示している企業や業界を特定させ、その情報をもとにメールマガジンを作成させるといった活用法も考えられます。
AI生成ツールの基本機能と注意点
AIツールの活用においては、その仕組みを理解することが重要です。
ChatGPTやMicrosoft Copilotなどの生成AIでは「自然言語処理(NLP)」と呼ばれる高度な技術が活用されています。これは、人間の言葉のパターンや文脈を機械が学習し、人間に近い自然な文章を生成できるようにする技術です。
もっとも、「AIが作ったコンテンツって本当に大丈夫?」という不安もありますよね。生成AIを導入・活用する際には以下のような注意点があります。
- 権利(著作権・商標など)侵害のリスク:学習データに基づき生成される内容が、元のコンテンツに酷似してしまう可能性があります。万一他社の著作物と似通った文章をAIが出力した場合、著作権侵害と見なされる恐れもゼロではありません。公開前に類似コンテンツがないか確認し、必要に応じて文章を修正する配慮が必要です。
- 情報の正確性(ハルシネーション): 生成AIの出力する文章は一見もっともらしくても、事実と異なる内容や根拠不明な情報が紛れ込むことがあります。インターネット上の誤情報を学習してしまっていたり、AIが文脈を誤解したりすると、間違った回答が平気で出てくる現象を「AIの幻覚(ハルシネーション)」と呼びます。従ってAIが書いた文章は必ず人間がファクトチェックすることが欠かせません。
- 機密情報の取り扱い:ChatGPTなど一般的な生成AIでは、入力したプロンプト(指示文)やデータが外部に漏洩するリスクも指摘されています。実際、入力内容が学習に使われ他のユーザーへの回答に活用されるケースも報告されています。そのため社外秘の情報や個人データはAIに入力しないのが鉄則です。社内で生成AIを導入する際は「機密データは入れない」など明確なルール策定と社員教育やガバナンス体制の構築も重要です。
また、「AI生成のコンテンツをGoogleは評価しない」といった話も聞いたことがあります。こちらに関してもGoogleの見解も調べてみました。
Googleは、検索順位の操作を目的としたコンテンツの自動生成をポリシー違反としています。ただし、完全に使用を禁止しているわけではなく、有用で信頼性の高いオリジナルコンテンツであれば、AI生成でも上位表示が可能です。

AIを補助的なパートナーとして位置づけることが重要です。得意分野はAIに任せつつ、最終的な判断や仕上げは人間が担う。このバランス感覚が、AI活用の成否を左右する要素となるでしょう。
HubSpot Content Hubコンテンツ生成でAIはどう活用できるのか
今回はHubSpot Content HubのAIを使ってコンテンツ生成に取り組んでいきます。その前に、まずはどのような機能があるのかを確認しましょう。
アイデア出し・構成案作成
みなさんは今、コンテンツのアイデア出しやブログ記事構成案の作成はどのように実施していますか?現状アイデア出しはChat GPTやGeminiなどのAIツールを活用している人も多いのではないでしょうか。
実はHubSpotにもアイデア出しに活用できるAI機能が存在します。「Breeze Copilot」という機能です。対話型AIツールとなりますが、強みはHubSpotの入っているデータを活用したインサイトを提供してくれる点です。ブログの構成案だけであれば、Chat GPTなど別のAIツールを活用しても問題ないかと思いますが、複数のページやツールを行き来することなくHubSpot上で一気通貫で作業を進められる点は便利です。

(出典:HubSpot Japn)
今回は「CRM SFA 違い」というSEOキーワードをターゲットにしてブログ記事を作成していければと思っています。実際にSemrushで調べて見ると、1,000もの月間検索平均数がありました。ユーザーの検索意図を理解し、ユーザーのニーズに答えるブログ記事をHubSpot AIを活用して作成していきます。

余談ですが、検索数とKW難易度であればHubSpot上でも確認することが可能です。HubSpotのSEO機能はSemrushのデータを参照しています。簡単な月間検索数とKW難易度を知りたい場合はHubSpotも活用できる点を覚えておくと便利です。

ブログ記事を作成する際に重要視していることは、検索キーワードの検索意図です。ユーザーがどういった情報を知るために検索しているのかその背景を想像・予測してブログ構成案を作成していきます。
AIによる自動コンテンツ作成と校正
コンテンツは、ゼロから作るのが一番大変だと思います。
構成案の作成は慣れてくれば楽ですが、実際の制作はなかなか大変です。ただ、HubSpotのAIを使えば、「CRMとSFAの違い」といったテーマを入力すると、導入文から見出し構成、各ポイントの整理まで、記事の流れを数秒で提案してくれます。
そして、作れるコンテンツの種類が多いのは魅力的です。
- ブログ記事
- ポッドキャスト
- ウェブページ/LP
- 営業用メール/ステップメール
- SNS投稿
- ナレッジベース

そして、HubSpot AIのすごいところは、書いた後の手直しもボタンクリックでお任せできることです。
文章のトーンを少し柔らかくしたいときや、長すぎる部分をコンパクトにしたいときってありますよね。そんなときは「文章を簡潔にする」「よりプロフェッショナルな口調にする」等、クリックするだけ。Breeze Copilotが一瞬で書き直してくれます。人間が行うと時間のかかる校正・推敲作業もAIに手伝わせることで、担当者はコンテンツの戦略やクリエイティブな部分に集中できるでしょう。

HubSpot 料金プランとAIコンテンツ生成
HubSpotでは、AIを活用したコンテンツ生成機能が各料金プランに応じて段階的に提供されています。
HubSpotは様々なAI機能を提供しています。その中でもコンテンツ生成機能に関連するAI機能は下記です。
- Breeze Copilot
- Breeze Agents (コンテンツエージェント、SNSエージェント)
HubSpot Copilotは業務の効率化と生産性向上を支援する対話型AIツールであり、HubSpotの全プラットフォームで活用できます。この機能は無料で誰でも活用可能になるので、ぜひ積極的に利用してみてください。
Breeze AgentsはそれぞれのHubのProfessional以上の契約が必要になります。例えば、ブログ記事やLP、事例記事作成などを支援するコンテンツエージェントはContent HubのProfessional以上のライセンス、SNSの投稿やクリエイティブなどの作成を支援するSNSエージェントはMarketing HubのProfessional以上のライセンスが必要となります。
詳しい詳細を知りたい方は、ぜひ下記のブログ記事もご覧ください。
<関連記事>
・HubSpotのAI機能「Breeze」とは?業務効率化に役立つ機能を徹底紹介
また、最近Chat GPTのDeep ReseachにHubSpotのCRMデータを接続することが可能になりました。HubSpotアカウント内のお客さまデータやコンテキスト情報を取り込み、ChatGPTで専門家レベルの高度な調査や分析を実行することができます。
こちらはChat GPTの有料アカウントが必要ですが、HubSpotは全エディション(無料アカウントを含む)で利用可能になります。従来時間をかけていた分析作業やマーケティング活動が、Chat GPTと連携することで大幅な効率化が可能になりました。

(出典:HubSpot Japan)
HubSpot AIを活用してブログ記事を生成してみた!
それでは、ここからは実際にHubSpot AIを活用してコンテンツ生成をしていきます。まずはブログ記事の作成をしてみましょう。
今回のブログ生成における作成ワークフロー
今回のブログ記事生成は大まかに以下のステップで実施しました。今回の趣旨としてHubSpot AIを活用してみるということなので、Chat GPTやGeminiといった他の生成AIは利用せずに、あくまでもHubSpot AIのみで生成していきます。
- キーワード選定・アイデア出し(Breeze Copilot使用)
- 構成案制作(Breeze Copilot、Breeze Content Agent使用)
- コンテンツ執筆(Breeze Copilot、Breeze Content Agent使用)
実際の生成プロセス
今回はHubSpot AIを利用してSEO記事を作成していきます。
それでは、さっそく取り組んでみましょう。
まずはHubSpot Copilotに下記のプロンプトを入力してみました。意図としては、「CRM SFA 違い」と検索する人がどう言った情報を知りたいと思っているのか、ユーザーの意図をしっかりと反映したブログ記事の構成案を作成したいと思っているからです。
<入力したプロンプト>
「CRM SFA 違い」というキーワードを狙ったSEO記事を作成したいと思っています。このキーワードを検索する人が知りたいと思っていることを網羅して箇条書きで教えてください。
すると、HubSpot Copilotが下記のような返信をしてくれます。

意外としっかりとした内容で返信してくれたので、正直びっくりしました。同じプロンプトをChat GPT 4.5 にも入力してみたのですが、ほとんど同じ内容が返ってきているので、他のAIツールとも遜色ないのかなと思います。
この出力してもらった内容をもとにブログの構成案を作成してもらう下記プロンプトを再度入力しました。このプロンプトは自分で作成したのですが、プロンプト自体をHubSpot AIに作らせるとより作業を効率化できるかもしれません。
<入力したプロンプト>
あなたはSEOに精通したコンテンツマーケター兼ライターです。ターゲットキーワード「CRM SFA 違い」を狙ったSEOに強いブログ記事の構成案を作成してください。以下の要件を満たして構成案を作成してください。
【要件】
想定ペルソナ:CRMとSFAの導入を検討しているが、それぞれの違いや自社に必要なツールがどちらなのか明確に理解できていない中小企業の経営者やマネージャー層。
目的:読者が知りたいと思っている下記内容を網羅したSEOブログ記事の構成案を作成してください。
1. CRMとSFAの基本的な定義・意味
CRMとは何か(Customer Relationship Management/顧客関係管理)の説明
SFAとは何か(Sales Force Automation/営業支援システム)の説明
2. CRMとSFAが目指す目的・役割の違い
CRMの主な目的(顧客満足度向上、リピート促進、顧客管理全般)
SFAの主な目的(営業活動の効率化、営業プロセスの可視化・自動化、売上アップ)
3. 主な機能と特徴の違い
CRMの代表的な機能(顧客データ管理、メールマーケティング、カスタマーサポート等)
SFAの代表的な機能(営業案件管理、商談管理、営業レポート、自動アクション等)
4. 主なユーザーや活用場面の違い
CRMが向いている企業・ケース
SFAが向いている企業・ケース
5. 両者の共通点・重複する部分
CRMとSFAで重複している機能・領域について
最近の「CRMにSFA機能が含まれている」ツールが多い現状の解説
6. 導入のメリット・デメリット
CRM導入のメリット・デメリット
SFA導入のメリット・デメリット
7. 導入のポイント・選定方法
自社にはどちらが必要なのか?判断基準
導入時の比較ポイント・チェックリスト
8. 実際のシステム例・主要サービス紹介
代表的なCRMサービスとSFAサービスの例
兼用できる「両方の機能を持つ」サービスも紹介
9. 失敗・成功事例(ニーズに合わなかった事例等)
CRM/SFAそれぞれ導入の成功・失敗のパターン
10. よくある質問・まとめ
CRMとSFAのどちらを導入すればいいの?
併用の可否や注意点
【必要な要素】
- 魅力的でSEOに最適化されたタイトル(キーワード「CRM SFA 違い」を含めること)
- 導入文(読者の課題を明確にし、この記事で何を得られるかを伝える)
- 明確でSEOに適した見出し構造(H2、H3を使用し、キーワードを適切に挿入する)
- 各セクションで解説するべきポイントを箇条書きで提示
- 読者の理解を深めるための具体例を提示するセクション
- 導入検討時の注意点やよくある間違いに関するセクション
- 最後に簡潔なまとめとCTA(行動喚起)を入れる
この要件に沿った構成案を具体的に提示してください。
するとHubSpot Copilotが作ってくれたブログ構成案が下記です。想像以上に詳細な構成案を作成してくれました。リード文の部分に「中小企業の経営者やマネージャーの皆さまへ。」や「CRM SFA というキーワードで検索されたあなたに向けて」などと言った記載して欲しくない内容も含まれています。この点は、自分自身で内容を修正する、またはプロンプトを試行錯誤すればより自然な構成案や文章を作成してくれると感じました。
・魅力的なSEOタイトル案
「CRMとSFAの違いとは?選び方&比較ポイントを徹底解説」
・導入文(リード文)案
中小企業の経営者やマネージャーの皆さまへ。
「そろそろ顧客管理や営業活動を効率化したいけど、CRMやSFAって何が違うの?自社にはどちらが最適?」と悩まれていませんか?本記事では「CRM SFA 違い」というキーワードで検索されたあなたに向けて、両者の違いや選び方、導入の注意点まで分かりやすく解説します。この記事ひとつで、あなたの疑問やモヤモヤをすべて解消できます!
【H2】CRMとSFAの基本的な定義・意味【キーワード挿入】
- 【H3】CRMとは?(Customer Relationship Management/顧客関係管理)の意味と目的
- 顧客情報を一元管理し、顧客との長期的な信頼関係を構築する
- 代表的な活用例や導入背景
- 【H3】SFAとは?(Sales Force Automation/営業支援システム)の意味と特徴
- 営業活動を効率化・自動化し、売上を最大化する仕組み
- 代表的な活用例や導入背景
【H2】CRMとSFAが目指す目的・役割の違い
- CRMの主な目的(顧客満足度向上、リピート促進等)
- SFAの主な目的(営業活動の改善・効率化、商談の成約率向上等)
- 自社の現状で何を重視するべきかの考え方
【H2】主な機能と特徴の違い【比較表あり】
- 【H3】CRMの主な機能
- 顧客データ管理
- メールマーケティング
- カスタマーサポート ほか
- 【H3】SFAの主な機能
- 営業案件・商談管理
- 活動履歴の記録
- 営業レポート・分析
- タスク自動化 ほか
- 機能別の比較マトリクス表
【H2】主なユーザーや活用場面の違い
- CRMが向いている業種・企業規模・シーン
- SFAが向いている業種・企業規模・シーン
- 典型的な導入例・利用ケース(図や表で具体例)
【H2】CRMとSFAの共通点・重複する部分
- 両者で重複している主な機能・領域
- 近年増えている「SFA機能を内包したCRM」や統合型クラウドツールの現状
- 各メリットと注意点
【H2】導入のメリット・デメリット
- CRM導入のメリット・デメリット
- 顧客ロイヤルティの向上/運用の手間やコスト等
- SFA導入のメリット・デメリット
- 営業の属人化防止/現場のITリテラシー課題等
【H2】導入のポイント・選定方法
- 自社にはどちらが必要か?判断基準
- 現状の課題(受注率、顧客管理の煩雑さなど)に合わせて選ぶ視点
- 導入時の比較ポイント・チェックリスト
- 機能・費用・サポート体制・拡張可能性等
【H2】実際のシステム例・主要サービス紹介
- 【H3】代表的なCRMツールの紹介と特徴
- Salesforce、HubSpot、ZohoCRMなど
- 【H3】代表的なSFAツールの紹介と特徴
- eセールスマネージャー、Sansan、Sensesなど
- 【H3】両方の機能を持つ「統合型サービス」も紹介
- クラウド型オールインワンツールの最新事情
【H2】導入成功・失敗事例と具体例
- CRM導入成功・失敗パターン
- SFA導入成功・失敗パターン
- なぜうまくいったorいかなかったのか、具体的な事例
【H2】導入検討時の注意点・よくある間違い
- よくある失敗と注意点
- 社内定着/運用不足、目的の不明確化、現場とのミスマッチ等
- 導入・運用を成功させるためのコツ
【H2】よくある質問とまとめ(FAQ+まとめ)
- CRMとSFA、結局どちらを導入すればいい?
- 併用する場合の注意点
- 具体的な導入ステップのQ&A
- 記事全体の要点まとめ
【H2】行動喚起(CTA)
- まずは無料資料ダウンロードや無料相談のご案内
- 具体的な問合せ先やCTAボタンの設置促進
【ご参考】各セクションで解説するポイントは、見出し下で要点を箇条書き・具体例・表・図解などで読者が一目で違いを理解できる形にしましょう。
ファーストビューには「このページで何が分かるか」を箇条書きで冒頭に表示するとSEO的にも親切です。
記事全体で「CRM SFA 違い」というキーワードを意識して適度に挿入してください。
さらに詳細な本文作成や見出しごとのポイント例も必要であれば続けてご指示ください。
この作成した構成案を使って、AIにブログ記事執筆の依頼を実際にしていきましょう。
HubSpotの左横のバーから「コンテンツ」→「ブログ」と選択し、右上に出てくる「AIを利用して開始」を選択してブログ記事を作成していきます。

「AIを利用して開始」をクリックすると以下の画面が出てくるので、必要な情報を記載していきます。
「ブログ記事で扱う内容の重要なトピック、目標、主なポイントについて説明してください。」という入力箇所があるのですが、今回はすでに作成している構成案を入力してみました。

必要項目を入力し、次に進むとブログ記事タイトルを選択する画面になります。HubSpotが入力した内容からタイトルを作成してくれますが、自分で編集することも可能です。今回はすでにHubSpot Copilotに作成してもらったタイトルを利用しようと思います。

次に進むとドキュメントを追加する画面に移行します。ここでは、必要に応じて参照ファイルやドキュメントを追加することでブログ記事の内容のクオリティーを高めることができます。
もし何か追加できるコンテンツをお持ちであれば、利用することをおすすめします。
注意点としては、アップロードしたコンテンツやファイルの内容はHubSpot AIに活用されるのでセンシティブな情報を追加することは避けましょう。

HubSpot AIがターゲットキーワードやブログタイトルなどをもとに構成案を作成してくれます。今までの経験上、アイデア出しとしては活用できますが、構成案の質はそこまで高くないのでご自身で必ず確認・修正することをおすすめします。今回はすでにHubSpot Copilotを活用して作成している構成案を入力していきます。
追加できるH2の数ですが、全部で10個まででした。H2の数が多いブログ記事は、2回に分けて作成する必要がありそうです。


「ブログ記事を生成」をクリックすると、HubSpot AIが記事の執筆を開始します。1~2分間待つと記事が出力されました。

出力されたブログ記事は正直にいうと、全体的に情報量も少なく、ブログ記事として公開するにはあまり質の高いものとは言えません。まだブログ記事生成におけるHubSpot AIの進化はこれからというところでしょうか。
HubSpot Breeze コンテンツエージェントで作成したブログ記事

そのため、Breeze コンテンツエージェントではなくHubSpot Copilotに直接ブログ記事を作成してもらうように依頼してみます。下記のプロンプトを入力してみました。
<入力したプロンプト>
あなたはビジネスおよびテクノロジー分野に精通したSEOライターです。以下の要件に基づいて、「CRM SFA 違い」をターゲットキーワードとしたブログ記事を日本語で作成してください。
【ターゲットペルソナ】
- CRMとSFAの導入を検討しているが、それぞれの違いや自社に必要なツールがどちらなのか明確に理解できていない中小企業の経営者やマネージャー層。
【ブログ記事構成案】
※以下省略※
【執筆時の留意点】
- SEOを意識し、「CRM SFA 違い」をタイトル、見出し(H2, H3)および自然な範囲で本文中に盛り込む
- 読者が難解に感じる専門用語は避け、平易で分かりやすい言葉を使用する
- 各項目は具体的な事例を交えて説明する
- ブログ全体の長さ8,000~10,000文字を目安
HubSpot Copilotが執筆したブログ記事の方が詳細ではあるものの、箇条書きの羅列が多く少し物足りなさはまだ感じます。プロンプトの調整や自身での加筆が必要になってくると感じました。
HubSpot Copilotを利用して作成したブログ記事はこちら

ここまでHubSpot AIを活用してブログ記事を作成してみて正直な感想を共有できればと思います。
HubSpotのAIを使っていて、出力される文章のボリュームが少ないという印象がありました。
たとえば、同じテーマをChatGPTやClaudeに投げると、600文字以上のまとまった文章が返ってくるうえに、具体性や論理性、語彙の選び方も洗練されていて、読み応えがあることが多いです。
それに比べると、現時点でのHubSpotのAIは、ややライトな印象。
最初の一歩や流れの整理には便利なんですが、完成度の高いドラフトをそのまま使えるかというと、まだ少し物足りないかなというのが率直な感想です。
なので今現状だと下記のように使い分けするのが良いでしょう。
- HubSpot: トピッククラスターの設計やキーワード選定など、SEO設計や構造づくりの支援に活用
- ChatGPTやClaude: 実際の文章制作やリライト、文章の質を求める作業に活用
このように目的によってAIをうまく使い分けることで、より効率よく、質の高いコンテンツ制作ができるようになるかと思います。生成AIの数は多々あり、それぞれ得意・不得意があります。大事なのは、何をどこまで任せるかを自分なりに見極めることです。1つのツールに固執するのではなく、柔軟に使い分けできるようになりましょう。
HubSpot AIを活用してマーケティングEメール文面を生成してみた
ブログ記事は外注している企業も多いと思うんですが、リードに直接アプローチするメールマガジンは、自社で作成しているケースが多いんじゃないでしょうか。
たしかに、メルマガはナーチャリングの要のため、外部には任せにくいです。それでいて、リードとの接点を絶やさず持ち続けるためにも、定期的な配信は欠かせません。だからこそ、ネタ出しや原稿作成がじわじわ負担になるのも事実です。
というわけで、ここからはマーケティングEメールもAIでどこまで作れるのかを試してみたいと思います。
今回のEメール生成におけるワークフロー
今回の検証では、HubSpotのAIアシスタント機能を用いて、ウェビナー告知用のEメールを一から作成しました。
ウェビナーは弊社が主催した「マーケティング・営業だけではない! HubSpot CRMを業務アプリとして使いこなす活用術」。対象は、過去に資料請求やイベント参加などの接点があった既存リードで、BtoB企業のCRMシステム担当者、DX担当者、HubSpotの既存ユーザーを想定しています。
今回の作業の流れは、ざっくりこんな感じでした。
- HubSpotにログイン
- Eメール作成画面を開く
- AIにプロンプトを与える
- 出力された文章を修正
- 配信設定して完了
実際にやってみたことで、「どこまでAIに任せられるのか」「どのタイミングで人の手を入れるべきか」が、かなりクリアになってきました。
ではさっそく、制作に取りかかっていきましょう。
実際の生成プロセス
まずは、HubSpotのダッシュボードにログインし、上部メニューから「マーケティング」→「Eメール」へと進みます。
作成画面では、これまでに作ったメールの一覧が表示されますが、今回は「Eメールを作成」をクリックして新規作成に進みます。

テンプレートの選択画面では、用途に応じていろんなタイプが選べます。今回はAI機能の検証が目的なので、「通常レギュラーEメール」を選び、テンプレートには頼らずゼロベースで作ることにしました。
編集エディタ画面が開いたら、まず件名・差出人・プレビュー文などの基本情報を入力。
そして、本文編集エリアをクリックすると、右上に「AIアシスタントを使って作成」というボタンが現れます。これを押すと、プロンプト入力のポップアップが出てくるので、以下のような指示を入れてみました。
「以下イベントへの参加を促すメール文面を作成して。トーンは親しみやすく、かつプロフェッショナルに。
##イベント情報
イベントLPの内容をコピペ」

数秒でAIが本文を生成してくれたのですが、やはりプロンプトがざっくりしすぎていたのか、やや抽象的で淡白な文章になってしまいました。また、URLのページの情報を正しく取得できていないため、URLを貼り付けるのではなく、イベントの詳細テキストを貼り付けた方が正しい情報をインプットしてくれるのではないかと思いました。
そこで次は、構成も含めて具体的に指示をしてみました。
「以下構成にもとづいてイベントへの参加を促すメール文面を作成して。
##構成
ウェビナー参加者の課題の提示
この課題を解決するためにウェビナーを開催すること
ウェビナータイトル
開催日時
ウェビナーの内容
参加して得られる期待
申し込みページへのCTA
##イベント内容
※LPの内容をコピペして貼り付けます※

最初のメール本文よりもイベント内容を反映したメール文面ができましたが、LPと内容がほとんど変わっていません。おそらくLPの内容を少し整理してまとめたものだと思います。そのため、一からメール文面を作成するよりは効率的かと思いますが、自分で読者の興味を引くように文言を変えるなど工夫が必要であると感じました。
メール作成におけるHubSpot AIで便利な部分は、メール本文から直接文章の修正や調整ができる点です。この部分の文章をもう少し詳細にしたい、短縮したい、ブランドトーンを反映させたいなど、細かな要望に沿ってHubSpot AIが調整してくれます。

本文が仕上がったら、次は件名の提案もAIにお任せしてみました。
「このメールマガジンの件名案をいくつか出して。ターゲットが思わずクリックしたくなるような件名にして」といったプロンプトを入力したところ、下記10案を出してくれました。
メールのタイトルはクリックしてもらうために非常に重要で、いつもかなりの時間を費やしてアイデア出しをしています。AIがすぐに案を出してくれるのは、非常に便利です。

今回のプロンプトでは、ユーザーが思わずクリックしたくなるようにと感情的なフックを指示したのがポイントです。他にも、限定感を出す、専門性を強調するなどの演出を加えるのもおすすめです。
最後に、配信対象のセグメント(今回はBtoB企業)を指定し、配信スケジュールを設定して完了。
今回の作業を通して感じたのは、HubSpotのAIはメールマガジン制作に十分活用できるということです。最初のプロンプト設計には少し時間がかかりますが、一度作ってしまえば繰り返し使えます。
もちろん、AIの出力はあくまでたたき台です。でも、白紙から文章を考える手間やストレスを大幅に軽減してくれるのは間違いありません。特に、メール配信数が多くなりがちな月末やキャンペーン時には、AIを活用することで時間を節約し、他の戦略業務に集中できる余裕が生まれます。
私自身、メールマガジンの制作には、HubSpotのAIを積極的に使っていきたいと強く感じました。
HubSpot AIを活用してソーシャルメディア投稿を生成してみた
今や業界を問わず、ソーシャルメディアは重要な集客チャネルになっています。でも、だからこそ「毎日の投稿が地味にしんどい…」と感じることも多いのではないでしょうか。
私自身、忙しい日には「とりあえずブログのリンクだけ貼っておこう」とか、「なんかありきたりな紹介文になってしまったな」と反省することがよくあります。とはいえ、SNSは継続的に届けることが大事なので、手を抜きすぎるわけにもいきません。
そこで今回は、HubSpotのAIアシスタントを活用して、SNS投稿をどこまで自動化できるのかを実際に試してみました。
今回のブログ生成におけるワークフロー
今回の検証では、弊社が公開している事例記事であるStringo社の日本展開に関する内容を題材に、HubSpotのAIアシスタントを使ってソーシャルメディア用の投稿文を作ってみました。
投稿先として想定したのは、X(旧Twitter)とFacebook。それぞれ使うトーンやアプローチが少し違うので、プラットフォームごとの最適化も意識しています。
今回の作業フローはこんな感じでした。
- HubSpotにログイン
- ソーシャルセクションを開く
- AIにプロンプトを入力
- 出力された投稿文を手直し
- 公開設定・スケジュール登録
続くセクションでは、実際に使ったプロンプト例や出力された文面の質、修正時に意識したポイントなどをご紹介していきます。
実際の生成プロセス
まず最初に行ったのは、HubSpotのメイン画面から「マーケティング」>「ソーシャル」へ進むことです。ここでは、すでに連携されている各SNSアカウント(今回はLinkedInとX)を一覧で確認でき、投稿の作成・編集・スケジュール管理をまとめて行えます。

「ソーシャル投稿を作成」ボタンをクリックすると、新規投稿エディタが開きます。ここで対象となるSNSを選び、投稿文を入力する欄をクリックすると、右側に「AIアシスタントを使ってコンテンツを生成」というボタンが表示されます。

このボタンを押すと、プロンプト(AIへの指示文)を入力するウィンドウが立ち上がります。まずは以下のようなプロンプトを入力しました。
あなたは8年目のコピーライターです。以下の事例記事をもとに、X向けの投稿文を1投稿140字以内で作成してください。目的は、Xのタイムライン上で興味を惹き、記事クリックを促すことです。
ターゲットは、BtoBマーケティング、CRM/SFAの導入や改善に関心のある担当者(営業企画・マーケティング部門)です。
投稿文で守るべき条件:
書き出しで課題やインパクトのある事実に触れて読者の関心を引く
導入前と導入後の変化を簡潔に伝える
感情に訴える言葉を入れる
入力データ:
会社名:ストリンゴ
業種:ビークルムーバー(車両運搬機)の製造・販売
#課題
・欧米仕様のHubSpotが日本商習慣に合わず活用できていなかった
・営業活動の進捗や成約率が見えず、戦略判断が曖昧だった
・CRMへの心理的抵抗が強かった
#成果
・営業プロセスをリアルタイムで可視化
・日本市場向けCRMを再構築し、運用定着
・その日本モデルがグローバルにも展開されるベストプラクティスに
ちょっと長めに見えますが、指示が曖昧だと出力される内容もぼんやりするため、しっかり構成を伝えるようにしました。ちなみに、入力データの部分は記事から概要をコピペし、プロンプト作成時間を短縮しています。

こちらが実際にHubSpotのAIが出力したX向けの投稿文です。
全体としては少しの編集ですぐに投稿できるレベルだったので、満足度は高かったです。
ちなみに、プロンプト内の「X向けに書いてください」の部分を、「Facebook向け」「LinkedIn向け」などに変更するだけで、それぞれのプラットフォームに合った投稿文が生成されるのも便利でした。
コンテンツ生成におけるHubSpot AIの現状を考察
「HubSpot AIをコンテンツ生成でどこまで使えるの?」
私自身、BtoB領域でコンテンツを制作してきた立場として、実際にHubSpotのAIアシスタントを使ってみて、さまざまな気づきと限界、そして可能性を感じました。今回はその正直な所感をお伝えします。
AIとヒトの役割分担を明確に
AIが出力する文章は、構文がしっかりしていて読みやすいものが多いと感じました。とくにEメールの件名や冒頭文、SNSの投稿文のように、短文で明確な目的があるコンテンツにはかなり実用的です。
それに、プロンプトを工夫すれば、トーンや目的をある程度反映させることも可能。指示が明確なら、想定したターゲットに合う言葉選びや構成もきちんと寄せてきます。
ただし、やっぱりAIには文脈の奥行きがまだ足りないと感じました。
たとえば、以下のようなポイントです。
- 文章全体を通して読者の心理をどう動かすか
- 専門用語をどこまで噛み砕いて説明するか
- 読み終えたあとにどんな感情を残したいか
こうした部分は、やはり人間の感性が担うべき領域だと思います。また、インターネット上の情報をまとめているに過ぎないため、ありきたりなコンテンツに収まってしまいます。特にSEOにおいては、主観や独自ノウハウをまとめたコンテンツ制作の重要性が増しているため、構成案で具体的に指示をする、もしくは人間の手で編集をする必要があります。
ここまでの検証を通じて感じたのは、現時点でのベストな使い方は「下書きをAIに任せて、仕上げは人の手で整える」ことだということです。
あるいはその逆に、自分でざっくりと内容を一気に書き出して、それをAIに整えてもらうというアプローチもかなり有効だと感じています。この方法なら、文法や言い回しを気にせずに頭の中のアイデアをアウトプットできるので、発想のスピードを落とさずに、読みやすい文章に仕上げることができます。
他ツールとの併用がより効果的
改めて感じたのは、HubSpotのAIだけですべてを完結させようとすると、実務ではどうしてもギャップが出てしまうということです。
たとえば、オウンドメディア向けのブログ記事の制作に関しては、やや物足りなさを感じました。
先にも触れましたが、出力される文章量が少なく、内容もテンプレ的な印象が強め。とくに長文で構成力が問われる記事では、現時点ではChatGPTやClaudeの方が明らかに優れています。
一方で、メールマガジンやSNS投稿のような短め(800字程度)のコンテンツにおいては、HubSpotは良いパフォーマンスを発揮してくれます。件名案や冒頭文のトーン調整も含めて、スピード感と実用性を兼ね備えたツールとして活躍してくれます。
そのため私は、SEOツールでキーワード候補をリストアップ → HubSpotでトピッククラスターを構築という流れで運用しています。この組み合わせが、現状ではもっとも効率的かつ実用的だと感じています。
これはHubSpotに限らず、すべてのAIツールに共通する話かもしれませんが、いまだ完璧なAIは存在していないというのが現実です。だからこそ、各ツールの得意・不得意を把握したうえで、補完し合う形で併用するという考え方が必要になります。
どこをAIに任せて、どこに人の手や他ツールの力を加えるか。この「使い分けのセンス」が、今後のコンテンツ制作の質とスピードを左右してくるはずです。
倫理的・法的リスクと対策
ここまでさまざまな活用方法を試してきましたが、最後に触れておきたいのが、AIによるコンテンツ生成に伴う倫理や法務の問題です。
HubSpot AIも含め、多くの生成AIに共通しているのは、出典が明示されないまま文章が生成されるという点です。たとえば、公開されているウェブ記事や論文の一部を学習データとして取り込んでいた場合、出力された文章が、オリジナルの表現と非常に似てしまうケースも考えられます。
私自身も、そのリスクがゼロとは言い切れないと感じています。仮にそうした文章をそのまま公開してしまった場合、あとから著作権やパブリシティ権の問題として指摘される可能性もあるわけです。
また、BtoB領域で多いのが、企業名や個人名、取引の詳細など、機密性の高い情報を取り扱う場面です。うっかりそういった情報をAIに入力してしまうと、たとえHubSpotが安全設計されているとはいえ、情報管理の観点からは好ましくありません。少なくとも、社内の情報が外部ツールに渡ることに抵抗を感じる人がいて当然ですし、その懸念は無視できないと私は思っています。
まずAIが出力した文章は必ず人が目を通すべきです。文体やトーンの調整だけでなく、事実確認や権利関係に問題がないかを含めたチェックが必要です。さらに、HubSpotにどんな情報を入力してもいいのか、逆にどんな情報は絶対に入れてはいけないのか。この線引きを曖昧にせず、社内で明文化しておくことが重要だと思います。
加えて、AIの生成物を使うプロセスの中に、確認・修正・承認といった複数のステップを設けることで、リスクを未然に防ぐこともできます。これはツールの性能の問題というよりも、運用設計の話です。どんなに優秀なAIでも、使い方を誤れば逆効果になる。その前提に立って、安全かつ責任ある活用をどう仕組みに落とし込むかが問われていると感じています。
まとめ
今回は、HubSpotのAI機能を使って、ブログ記事・メールマガジン・SNS投稿といったコンテンツを実際に作成してみました。
そのうえで感じた率直な感想は、すべてを任せきるにはまだ物足りないけれど、業務効率化の観点ではしっかり役立ってくれるということです。
特にブログ記事の生成に関しては、まだ文章量や深みの面で課題が残ります。一方で、メルマガやSNS投稿といった中〜短文コンテンツには相性が良く、実務的な価値が高いと感じました。
HubSpotならではの強みは、一気通貫でコンテンツを回せるという体験設計とCRMとのシームレスな連携です。
アイデアの着想から下書き、構成、CTA挿入、投稿、配信分析まで、すべてをHubSpot内で完結できる。この導線は他の生成AI(たとえばChatGPTやGemini)にはない大きな魅力です。さらに、CRM上のリード情報を参照しながら、ペルソナ別・ステージ別にパーソナライズされた文章を生成できる点も、BtoB企業にとってはかなり現実的な利点だと思います。
とはいえ、生成精度や自由度という点では、やはり汎用型の生成AIに軍配が上がる場面も多くあります。たとえば、競合サイトのURLを渡して構成案を出すとか、記事全体のトーンを緻密に調整するといった使い方は、HubSpotではまだ難しいと感じました。
全体的に決められた流れを効率よく処理することが得意な印象です。
このあたりを踏まえると、現状のHubSpotのAIは戦略的なコンテンツ設計を担うものではなく、実務での配信・運用を効率化する道具として位置づけるのが妥当だと思います。今後もHubSpot AIは日進月歩で進化していくので、新しい機能やアップデートに注目です!
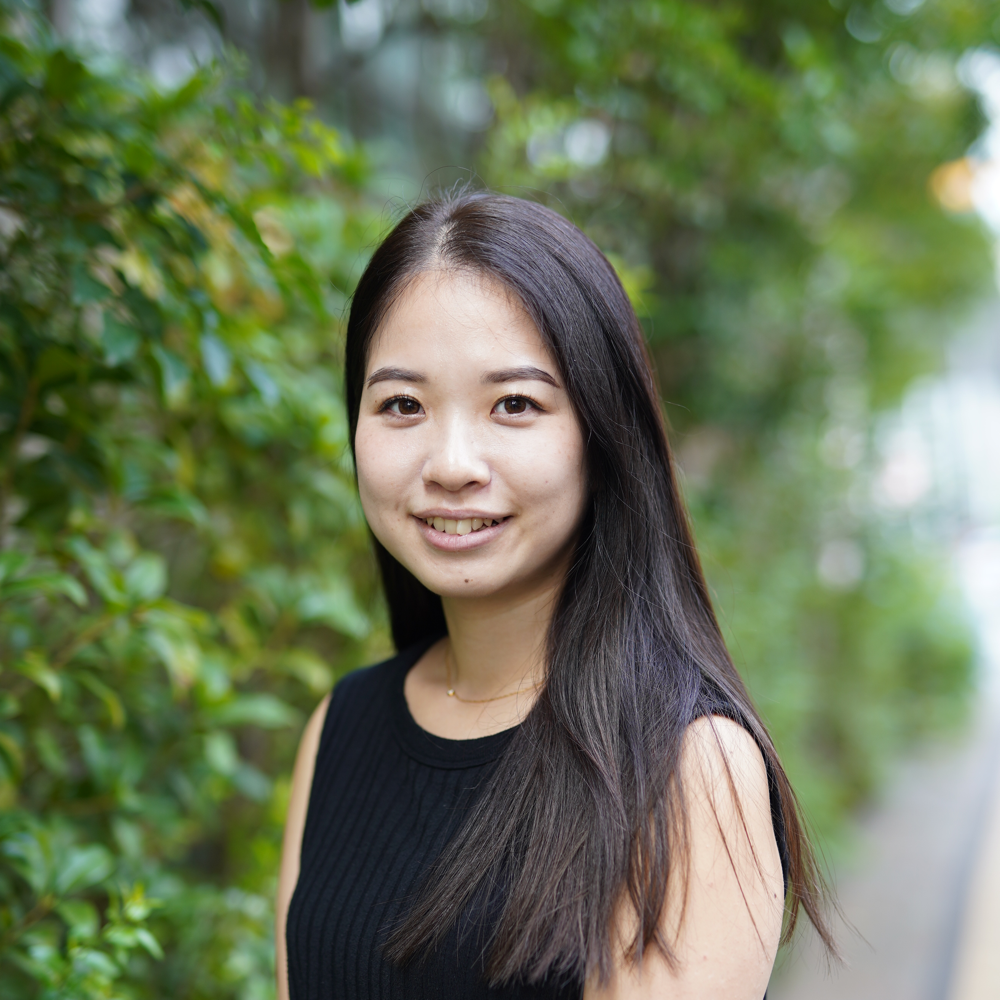
渋谷 真生子
株式会社100(ハンドレッド)のマーケター。新卒でグローバルヘルスケア企業で営業を経験し、セールスフォースにてBDRとして地方企業の新規開拓に携わる。コロナ渦でインバウンドマーケティングの重要性を実感し、アイルランド ダブリンにあるトリニティカレッジの大学院にてデジタルマーケティングの学位取得し現在に至る。最近はかぎ針編みにハマり中。
We are HubSpot LOVERS
ビジネスの成長プラットフォームとしての魅力はもちろん、
HubSpotのインバウンドマーケティングという考え方、
顧客に対する心の寄せ方、ゆるぎなく、そしてやわらかい哲学。
そのすべてに惹かれて、HubSpotのパートナー、
エキスパートとして取り組んでいます。
HubSpotのこと、マーケティング設計・運用、
組織の構築など、どんなことでもお問い合わせください。